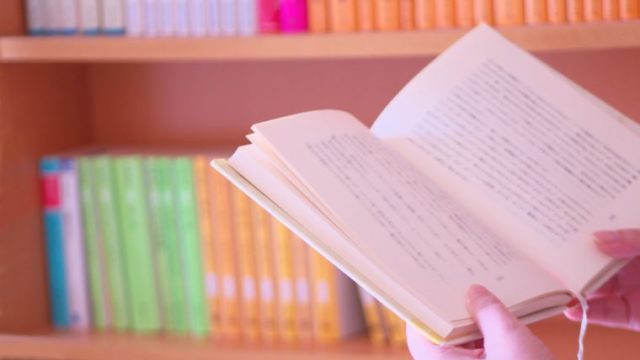みなさんは将棋を行いますか?今回は将棋の8大タイトルとその種類を分かりやすくお伝えします。
近年、将棋界に現れた若き天才、藤井聡太棋士の影響で将棋ブームが起きています。藤井棋士の戦いがあるとメディアはこぞって取り上げ、これまで全く将棋に関心がなかった方、ルールも詳しくない方が藤井棋士の「ファン」になって応援しています。90年代に起きた羽生善治棋士のブームを上回り、このようなことは将棋界において未だかつてない出来事でしょう。
また、このブームは子や孫の世代にも影響を与えています。藤井棋士のようにさせたい親や祖父母が将棋教室へ通わせたり、将棋盤を購入し、始めさせたりするケースも増えています。
今回はそんな将棋界の天才、藤井棋士がいくつも獲得していっているタイトルの中で8大タイトルと呼ばれるものをご紹介します。「8大タイトル」とはどんなものかから始まり、それぞれの予選、タイトル獲得戦や賞金。どのような人が羽生棋士のような永世名人になるのかをご紹介します。
これを読めば、藤井棋士の試合により詳しくなれること間違いないでしょう。
目次
将棋8大タイトル

将棋8大タイトルとは
タイトルというと「(本などの)題名」という意味で使われることが多いのですが、将棋の場合「タイトル」は「称号」という意味です。テニスで言う「○○オープン」といった4大タイトル、ボクシングの○○級タイトルと同じ意味です。
現在、プロ棋士は220人以上いると言われています。これら棋士界の王者を表す称号が8つあり、これを8大タイトルといいます。
竜王(りゅうおう)、名人(めいじん)、王位(おうい)、王座(おうざ)、棋王(きおう)、叡王(えいおう)、王将(おうしょう)、棋聖(きせい)の8つです。
タイトルには序列がある
8個あるタイトル。それぞれタイトルを持つということはすごいのですが、タイトル自体に序列(ランク)があります。一番上が竜王です。その次に名人、王位、王座、棋王、叡王、王将、棋聖という順です。この序列はタイトルの歴史や賞金額などでできました。今回はこの序列の順番で紹介します。
8大タイトルそれぞれの特徴

ここからはそれぞれのタイトルやタイトル戦の特徴を紹介します。タイトル戦はそれまでの王者(タイトル保持者)と予選を勝ち進んだ挑戦者が戦うのです。
タイトルごとに挑戦者の決め方やタイトル戦の方法、賞金、主催者が異なります。ここからはこういった違いを分かりやすく紹介します。
竜王戦-読売新聞社主催
竜王は(次に紹介する)名人と並び棋士界の頂点のタイトルと言われています。
挑戦者の決め方
予選
最初に行われるのがランキング戦です。これは階級ごとで1~6組6つに分かれてトーナメント戦を行います。
第6組には女流棋士やアマチュア竜王戦の上位数名も参加できます。
決勝トーナメント(挑戦者決定トーナメント)
ランキング戦各組の成績優秀者11人(上級の組から順に5・2・1・1・1・1名)で決勝トーナメントを行います。ここで優勝した人は、タイトル保持者と竜王の座をかけて戦う権利が得られるのです。
竜王タイトル戦
タイトル戦は7番勝負で行われ、先に4勝した方が竜王タイトルを獲得できます。1局当たり8時間の持ち時間があり、2日かけて行われます。
賞金(単位:万円)
- 竜王決定戦:勝者4320、敗者1620。
ランキング戦でも賞金が出ます。また、昇級や降級もあります。
名人戦-朝日新聞社と毎日新聞社主催
名人も竜王と並び将棋界の頂点と言われるタイトルです。
挑戦者の決め方
(竜王の場合は「組」でトーナメントを行いましたが)名人戦挑戦者は順位戦で決まります。棋士には段とは別に上からA級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組の5つの階級があります。そして、それぞれの階級には人数が決まっているのです。このうちA級10人の中で行われる順位戦優勝者が名人との挑戦権を獲得します。
この順位戦の階級は、名人戦以外の多くのタイトル戦でも用いられています。
A級の順位戦とは
A級棋士の総当たりで戦います。
A級には10人いるとお伝えしましたが、この順位戦にはそれまでのA級上位8人とB級上位2人の計10人で戦います。つまりこの順位戦でA級下位2人とB級上位2名が入れ替わります。
竜王戦はアマチュア棋士にもチャンスはありましたが、名人戦はA級にまで昇格しないと予選すら出られません。
名人タイトル戦
本戦は竜王戦と同じ、7番勝負。先に4勝した方が名人になります。違うところは持ち時間です。竜王戦が8時間なのに対し、9時間あります。
賞金(単位:万円)
- 本戦勝者1200、敗者300
- 対局料:それまでの名人1050、挑戦者400
- 名人手当:月100
王位戦-北海道・東京・中日・神戸・徳島・西日本各新聞社主催
挑戦者の決め方
予選
シードの4人を除いた全棋士と女流棋士2人(女流王位とその挑戦者)が参加する予選をトーナメントで行います。
挑戦者決定方法
シードの4人(前回の王位決定戦敗者、前回の挑戦者決定リーグ2位以上の人)と、予選を勝ち抜いた8人、計12人から選ばれます。
12人を6人ずつ2つのリーグ(紅白)に分け、それぞれの2つのリーグの中で総当たり戦を行います。そしてそれぞれのリーグで優勝者が戦う挑戦者決定戦(1局)で挑戦者が決まります。
王位決定戦
竜王戦と全く同じです。7番勝負で先に4勝した方が勝ち。持ち時間も8時間です。
賞金(単位・万円)
- タイトル戦勝者700、敗者300
- 対局料:それまでの王位500、挑戦者300
- 挑戦者決定リーグ対局料:200
王座戦-日経新聞社主催
挑戦者の決め方
一次予選、二次予選を勝ち進んだ5~12人とシードの11~4人。計16人で戦うトーナメントで決まります。
一次予選
トーナメント形式で行われます。出場できるのは(名人戦でお話しした)順位戦C級1組以下の棋士と女流棋士4人です。ここで上位6人が二次予選へと進みます。
一定の条件を満たす棋士は一次予選を免除され、二次予選から戦います。
二次予選
二次予選もトーナメントで行われます。一次予選で勝ち残った6人と、一次予選を免除された人たちで争います。ここで勝ち進んだ5~12人が挑戦者決勝トーナメントへ進むのです。二次予選から決定トーナメントに進む人数はその時のシード者の数により決まります。
挑戦者決定トーナメント
挑戦者は二次予選上位者とシード者のトーナメントで決まります。シード者は(他の)タイトル保持者と前回大会での上位4人です。
王座決定戦
ここまでのタイトル戦は先に4回勝った方が優勝する7番勝負でしたが、王座戦は5番勝負。先に3回勝った方が王座を獲得できます。持ち時間は5時間。1局が1日で終わります。
賞金(単位:万円)
- 王座決定戦勝者700、敗者300
- 決定戦対局料:前回の王座500、挑戦者300
- 本戦迄の対局料:約300
棋王(きおう)戦-共同通信社主催
挑戦者の決め方
予選
予選はトーナメントで行われます。順位戦B級2組以下の棋士と女流棋士1人、アマチュア名人1人で戦い、上位8人が挑戦者決定トーナメントに進みます。
女流棋士やアマチュア名人が挑戦者決定トーナメントに進むと、プロ棋士になるための試験「棋士編入試験」の受験資格が得られます。
挑戦者決定トーナメント
挑戦者決定トーナメントは以下の30人余りで戦われます。出場者は以下の通りです。
- 予選を勝ち進んだ8人(トーナメント戦のシードが与えられ2回戦から出場)
- 前回の挑戦者決定トーナメントでの上位4名(前回棋王戦敗者も含む・トーナメント戦のシード権があり、3回戦から出場)
- 順位戦B級1組以上
- (他の)タイトル保持者
棋王戦挑戦者決定トーナメントには敗者復活戦があるのが特徴です。
棋王決定戦
王座戦と同様、5番勝負。先に3勝した方が棋王となります。ただし王座戦は持ち時間5時間でしたが棋王戦は4時間です。
賞金(単位:万円)
- 本戦勝者500、敗者200
- 本戦対局料:前回の棋王400、挑戦者100
- 本戦までの対局料:約300
叡王戦-不二家主催
現在叡王戦はペコちゃんでおなじみの不二家が主催で行われています。2017年にタイトル戦に格上げされた一番新しい称号です。
挑戦者の決め方
予選
段位ごとのトーナメントで行われます。持ち時間はたったの1時間。なくなったら1手60秒未満内となります。ここでの上位12人が挑戦者決定トーナメントへ進みます。
挑戦者決定トーナメント
挑戦者決定トーナメントは、段位別の予選を通過した12人と、前大会上位4人の16人で争います。持ち時間3時間。なくなったら1手60秒未満内です。
叡王決定戦
叡王戦は棋王戦と全く同じです。5番勝負で持ち時間4時間で行います。
賞金(単位:万円)
- 優勝賞金1200
- 対局料400(防衛するとさらに400)
王将戦-スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社主催
挑戦者の決め方
一次予選、二次予選のトーナメント戦の後、リーグ戦で挑戦者が決まります。
一次予選
順位戦B級1組以下の方のトーナメント戦で行います。各組のトーナメントで勝ち上がった人が二次予選へ進みます。
二次予選
二次予選もトーナメント戦で、以下の18人から3人が次の挑戦者決定リーグへ進みます。
- 前回の挑戦者決定リーグの下位3人(トーナメント2回戦から出場)
- (他の)タイトル保持者
- 一次予選通過者
- 順位戦A級の棋士
- 永世王将
挑戦者決定リーグ
二次予選を通過した3人と前大会の挑戦者決定リーグ上位4人(前王将戦での敗者を含む)の合計7人の総当たりをします。その後上位2人がプレイオフして挑戦者が決まります。
王将決定戦
七番勝負で先に4勝した方が勝ちです。持ち時間は8時間です。
賞金(単位:万円)
- タイトル獲得者:500
- 対局料:前回の王将300、挑戦者100
- リーグ戦対局料約200
棋聖戦-産業経済新聞主催
挑戦者の選び方
一次予選
順位戦C級1組以下の棋士と女流棋士2人のトーナメント戦で、上位8人が2次予選に進みます。持ち時間は1時間です。
二次予選
以下の方々のトーナメントで上位8~12人が選ばれます。持ち時間1局当たり3時間です。
- 一次予選を勝ち抜いた8人
- 前回決勝トーナメント5位以下
- 棋聖決定戦出場経験者
棋聖挑戦者決定トーナメント
以下の16人で行うトーナメント優勝者が棋聖戦挑戦者となります。持ち時間は4時間です。
- 前回決勝トーナメント4位以上
- 他のタイトル保持者上位4人
- 二次予選を勝ち抜いた8~12人
棋聖決定戦
五番勝負で3勝した方が棋聖となります。1局当たりの持ち時間は4時間です。
賞金(単位:万円)
・優勝賞金700
タイトル保持者の呼び方

はじめの方でタイトルは称号と話しました。そのためタイトルを取ると呼び方が変わってきます。
例えば山田さんという棋士が3段だったとします。すると「山田3段」と呼びます。しかしタイトル(例えば叡王)を取ると山田叡王といったように名前の後に段位ではなくタイトル名が付くのです。
また藤井聡太棋士のように複数のタイトルを獲得している人は藤井6冠。または獲得したタイトルの中で(最初の方でお話しした)序列の一番上の称号、例えば藤井竜王と呼びます。
最後に~永世名人とは
いかがでしたでしょうか?将棋8大タイトル戦には、それぞれ異なった方法で挑戦者が決められ、賞金などにも違いがあることが分かっていただけたかと思います。改めて藤井聡太棋士のすごさが分かったのではないでしょうか?
最後に羽生善治棋士が持つ「永世名人」という称号についてご紹介します。実は「永世○○」という称号は名人にだけあるではなく、各タイトルにあります。それぞれの称号で決められた回数タイトルを獲得・保持すると「永世○○」という称号が得られます。
ちなみに永世名人には通算5回獲得するとなれます。藤井聡太棋士がいつか永世称号を獲得する日を待ちながら応援しましょう。