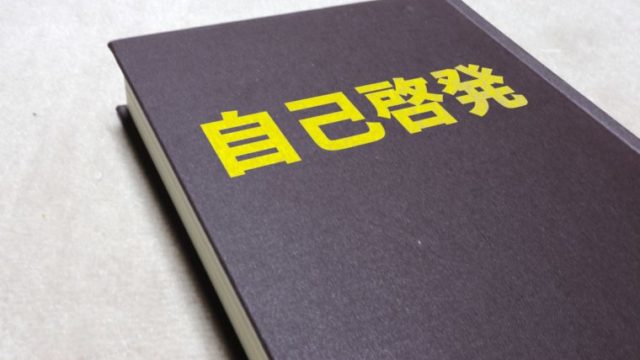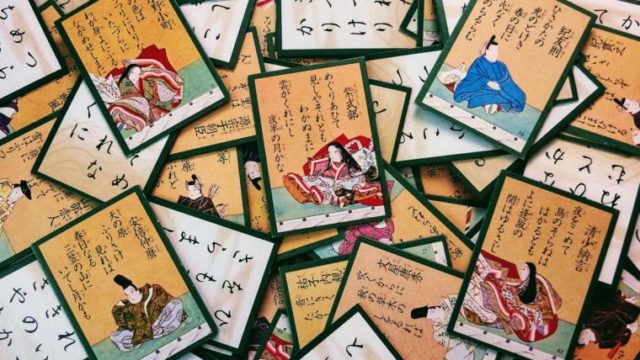2月3日は節分です。節分の食べ物と言われて何をイメージしますか?おそらく豆まきに使う大豆をイメージする人が多いはず。しかし地域によって大豆以外の食べ物があることを知っている人は少ないと思います。
節分の食べ物は縁起がいい食べ物が選ばれるのは同じ。当然、地域によって縁起のいい食べ物が違います。たとえば「いわし」や「けんちん汁」、あるいは「鯨(くじら)」を食べる地域もあり、知らない人からすれば驚きです。
なぜ縁起物が選ばれるのでしょう?それは旧暦で節分は現在の大晦日になるからです。今も年越しは特別な日。当時も新たな年がよい年になるようにと縁起を担いだのは想像ができます。この記事では、節分に食べる物と、節分祭にオススメなスポットを紹介します。最後まで読んでいただけると幸いです。
こちらの記事も参考にしてください。
節分の由来~鬼滅の大豆で邪気を払い、1年間の無病息災を願おう~
おもな食べ物

大豆
節分の日で一番、食べられているのが大豆。大豆は昔から病や災いを払う力があると考えられていました。節分は豆をまく行事ですが、豆まきの風習は室町時代に中国から伝わった「追儺(ついな)」という行事から誕生しております。節分と言えば豆まきですが、実は室町時代に中国から伝わった風趣です。
恵方巻
関西地方の商人が商売繁盛、無病息災を祈願したのが最初。今では誰もが知る恵方巻ですが、ここまで有名となった説として1980年代後半にコンビニが季節商品として太巻きを販売した影響が大きいです。最近では、長さが半分のハーフサイズの恵方巻もあります。
いわし
関西を中心に西日本に残る「いわし」。西日本では、いわしのにおいを鬼が嫌うと考えられ、食べたいわしの頭を玄関先に飾り厄除けをする地域もあります。他の地域からみたら、玄関先にひいらぎの葉がついた枝先に焼いたいわしの頭が刺さっている光景は驚きです。
けんちん汁
関東の一部の地域に残る「けんちん汁」。由来は諸説あり、中国の精進料理説「巻繊(けんちゃん)」が日本語になったという説と、鎌倉時代に食べられていた「健長汁(けんちょうじる)」が「けんちん汁」へと呼び方が変化したという説です。寒い時期に温かい汁物を飲んで身体を温めるという意味に変わりがないと言えます。
節分は大寒なので、寒い日に身体を温めるのは昔から変わらないと言えます。
鯨
山口県に残る「鯨」を食べる風習。「大きく健康に育つように」「心を大きく」といった願いを込めて鯨が食べられます。
鯨を食べる機会が少ない現在では、鯨を食べる貴重な風習です。
こんにゃく
四国地方に残る「こんにゃく」を食べる風習。こんにゃくは別名「砂おろし」とも呼ばれます。体内の毒素を抜き、清らかな身体となって1年を迎えるため食べられます。
身体の毒素を洗い流すこんにゃくですが、なぜ節分の日に食べられるのかは不明です。
麦飯
中国地方でも麦作が盛んな広島、岡山、島根、山口県で「麦飯」を節分に食べる風習が残っております。麦飯は「世の中を回す」縁起物と考えられ、節分の日に麦飯を食べる風習が定着しました。
西日本では麦を「よすま」と呼ばれていたことから、「世を回す」と言われます。
ぜんざい
関西地方に残る「ぜんざい」風習。小豆には厄除けの力があるとされ、特に小豆の赤色は重除け効果が強いと言い伝えられております。
小豆の代表料理「ぜんざい」は厄除け効果がある赤色なので、当日は通行人にも振舞われます。
ぜんざい以外にも、小豆ごはんも厄除け効果があるとして振舞われます。
おすすめの節分祭

節分の食べ物は地域によって違うことがおわかりになったと思いますが、次はオススメの節分祭について3点紹介します。テレビのニュースなどでも取り上げられている有名なものをご紹介しているので、ぜひこの続きもご覧ください。
成田山新勝寺 千葉県
千葉県にある成田山新勝寺。毎年、節分の日になると大相撲の力士やドラマの出演者が参加して盛大に豆まきを行います。節分の日には、ニュースなどで見かけることが多い場所です。
八坂神社 京都府
京都祇園の八坂神社。八坂神社の節分は、舞妓・芸妓による舞踊奉納が行われます。八坂神社では、舞妓の豆まきが行われることが特徴です。
舞妓が豆まきをする光景は、祇園ならではの光景です。
多度大社 三重県
毎年2、3000人ほどの人手で賑わう節分祭。多度大社では節分の日が平日だと参拝できない人のために「特別豆まき」が毎年1月最後の日曜日に執り行われています。多度大社は一足早い節分祭です。
まとめ
節分と呼ばれる日は2月3日だけでなく、1年で4回あり、立春、立夏、立秋、立冬の境が節分です。ではなぜ2月3日の節分だけ、盛大に豆まきをするのでしょう?それは、旧暦で2月3日は今の大晦日と同じ意味があります。
節分に縁起を担いて新年を迎える思いは、現在の年越しに通ずるものがあり、その地域に伝わる縁起物を食べる風習が今も残っているのは興味深い事実です。各地で節分祭が執り行われますが、その地域に伝わる縁起物を見つけてみるのはいかがでしょうか?