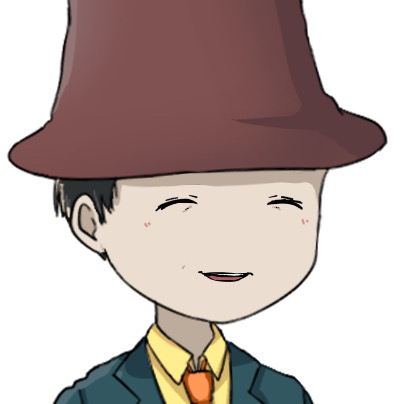皆さん節分と聞いて何を思い浮かべますか?豆撒きを一番に思い浮かべる方が多いと思います。家族で鬼役を決めて鬼のお面をかぶって豆をぶつけるお宅もあるだろうし、伝統的な、代々伝わる料理を作るお宅もあるでしょう。
「鬼は外」ではなく「鬼も内」といいながら豆を撒くお宅もあることをご存じですか?そもそもいったい豆撒きにはどんな理由があり、いつ頃から行われているのでしょう。節分とはどんな日で、どうして2月に行われるのでしょう。
今回はそんな日本の2月の伝統行事「節分」についてご紹介いたします。
目次
節分とはいったいどういう日

皆さん「節分」と聞くと豆まきや恵方巻などなどの2月の行事を思い浮かべると思います。もちろん2月3日(ごろ)も節分ですが、実は5月。8月、11月にも節分はあります。
節分とは「季節を分ける」と書きますよね。その名の通り季節を分ける日をさします。2月の節分が立春の前の日で「冬と春とが入れ替わる前日」なのと同様に、立夏の前日、立秋の前日、立冬の前日も節分と言います。
ではどうして2月の節分だけこんなイベントになったのでしょう。これには旧暦(太陰太陽暦)が関係します。
旧暦は月の満ち欠けの周期をひと月としていました。新月(しんげつ・月の満ち欠けで全く見えない状態の月)の日が月初めの日(1日、ついたち)です。そして旧暦の元日1月1日は「立春に最も近い新月の日」とされていました。
そんなこともあり旧暦のころは元日(旧暦の1月1日)と同様に立春も「新年を迎える日」ととらえられていました。その前日である2月の節分は大晦日と同様に「年越しの日」だったのですね。
節分は2月3日とは限らない

2021年の節分が2月2日だったのを覚えていらっしゃる方も多いかと思います。実は節分は2月3日とは限りません。2021年は立春が2月3日だったから節分は2月2日でした。
立春の日にちは太陽と地球の動きによって決まります。2月4日が多いのですが、2月3日になることもあれば逆に2月5日になる事もあります。立春が微妙に前後するため、その前日の節分も前後します。節分が2月2日になることもあれば、2月4日になることもあります。
節分と鬼や豆まき―「魔物を滅ぼす」

日本では平安時代から節分の風習がありました。これは中国にあった風習が日本に入ってきたものです。
中国では冬から春にかけて「疫鬼(えきき)」という妖怪が疫病や災難が起こすとされていました。だから「新しい年に向けてこの疫鬼を追い払う」風習があったのです。この風習が平安時代に日本に入り、宮中の行事「鬼遣(おにやらい)」になりました。
豆を撒く風習は室町時代に始まりました。「魔物を滅ぼす」を略して「魔滅(まめ)」となり災いを追い払うために「豆」を撒くようになりました。
鬼滅の刃ならぬ『鬼滅の大豆』とでもいうのでしょうかね。
「鬼は外」ではなく「鬼は内」のところ

豆撒きの時に掛け声に「鬼は外、福は内」と言うのが一般的だと思います。でもお寺や神社、地域やお宅によっては「鬼は外」ではなくて「鬼は内」と言います。
ここで問題です
どういったお寺や神社、地域やお宅で『鬼は内』と言うのでしょう・・・?
Thinking timeスタート
・
・
・
正解は「おに」に関係があるお寺や神社、地域やお宅で「鬼は内」と言って豆撒きをします。
例えば、
お寺や神社であれば鬼神様を祭られているところ。
苗字に「鬼」の漢字が入っているお宅。
地名に「鬼」の漢字が使われている所や、以前その地域を治めていた大名などの名前に「鬼」の漢字が含まれていた所・・・など。
さらにこんな地域も「鬼は内」と言います。
その地域は福島県の二本松市で、旧二本松藩があった一部の地域です。この二本松藩を治めていた大名が「丹羽氏」。「おには外」と言うと「大名を外に・・・」となってしまうからなのです。
皆さんのお宅では相槌(あいづち)を打ちますか?

豆撒きをする時に「鬼は外、福は内」と言い豆を撒く人の後ろで相槌を打つ家庭があるのはご存じですか?日本全国にこういった風習を受け継ぐ地域や家庭があります。すりこ木、すり鉢や杓文字などを持って「ごもっとも、ごもっとも」などと相槌を打つのです。神社でもこういった風習が残っているところもあります。
今でこそ子供たちが豆を撒く時代にはなりましたが、もしかしたら昔は家の主(あるじ)が豆を撒き、家族はその後ろで相槌を打っていたのかもしえませんね。
ヒイラギやイワシをなぜ飾る?

節分にヒイラギにイワシの頭を付けた「柊鰯(ひいらぎいわし)」を玄関に飾る風習がある地域があります。この柊鰯は主に西日本で見られる風習です。ヒイラギの葉っぱのトゲトゲとイワシのくさい臭いで鬼が寄り付かないようにと言う魔よけの意味があります。
恵方巻の発祥は大阪?

近年、節分の日にスーパーに並ぶのが恵方巻。「昔は自分の住む地域では恵方巻を食べる風習はなかったなぁ」と思う方も多いと思います。実は大阪発祥と言う説が有力とされています。
大阪の海苔業者の販売戦略で始めたという説や、豊臣秀吉の家臣が節分の日に巻きずしを食べて戦いに挑んだところ見事勝利を収めたところからという説がありますが、定かではありません。
「その年の恵方を向いて、何も話さずに食べきると願い事がかなう」と言われています。
ちなみに恵方とは歳徳神(としとくじん)というその年の福徳をつかさどる神様がいる方向です。毎年十干(じっかん。(干支が十二支あるのと同様に)甲・乙・丙・・から始まる10個の年を表す語)により、歳徳神がいる方向が変わり、恵方が決まります。
年の数プラス1個の豆を食べる

豆撒きの後、皆さんは歳の数だけ豆を食べるように幼いころから言われていたと思います。
でも小さい頃は「歳の数」では少ないのでそれ以上に沢山食べていたのは私だけでしょうか。
ではどうして豆を食べるのでしょう。
大豆は生では食べられません。節分の豆は炒って火が通してあります。大豆を炒ることで邪気を払われると言われ、邪気を払われた豆ということで「福豆」と呼ばれるのです。
福豆を食べるということは「1年間健康で過ごせますように」という願いが込められています。
でも実は歳の数ではなく本当は「歳の数より1個多く」食べます。これには「これから1年間の健康を願う」という意味が込められています。
近年では大豆ではなく落花生を撒くところも増えていますよね。「撒いた豆がもったいないから」という理由や、小さい子供が飲み込んだ豆が肺の方へ入ってしまう誤嚥(ごえん)を防ぐためという意味もあります。
節分に食べる各地の食べ物

日本各地、節分には「無病息災を願って」や「邪気を払う」ためにいろんな食べ物を食べる風習があります。その一部をご紹介します。
・西日本を中心に柊鰯と同様に鰯を食べて邪気を払うという風習があります。また、「鰯を焼く時の煙で鬼が近寄らない」という意味もあります。
・京都市にある廬山寺(ろざんじ)では蓬莱豆(ほうらいまめ)と言われる大豆の外側を砂糖でコーティング、紅白に色づけられた豆を1粒ずつ食べると寿命が延びると言われています。
・静岡県、遠州(えんしゅう)地方ではと厄年の人が厄払いに「なた餅(あんこの入った白餅にきな粉をまぶしたもの)」なるものを辻(交差点の脇など)に置くという習わしがあります。辻に置かれたなた餅は子供たちに食べてもらうことで厄払いが出来るといわれています。
・長野県の北部の地方ではとろろ汁を麦飯にかけて食べます。とろろ芋(長いも)を鬼の角に見立てて「角を擂(す)るような姿に見える」や、「ぬるぬる滑ってして鬼が家に入ってこられない」といった意味が込められています。
・山陰地方では江戸時代から「砂おろし」と称してこんにゃくを食べます。島根県の隠岐(おき)では「なまこ」を「砂おろし」として食べることからなまこの代替品としてこんにゃくが食べられるのではないのかとも考えられます。
「砂おろし」として食べられるようになったのはなまこの食事方法にからきています。
なまこは海の底の砂をそのまま食べて、砂に混じったりくっついたりしている有機物だけを吸収します。そして消化・吸収できなかった砂などを糞と共に排出するのです。こういったなまこの食事方法から、腸の中をきれいにするという意味で食べられています。
・北関東では「しもつかれ」という食べ物があります。節分に余った豆や正月に残った新巻鮭(あらまきじゃけ)の頭などと共に「鬼おろし」を使ってすりおろした大根やニンジンなどを酒粕(さけかす)や出汁で煮込んで食べます。
家庭ごとで味が異なり、余ったものは近所に配ります。7軒分のしもつかれを食べると「病気しない」とも言われています。鎌倉時代の説話(せつわ)にも出てくる食べ物で、2月の初午の日に作られる行事食です。北関東の各地で、呼び名は少しずつ異なります。
・また日本各地ではクジラを食べる風習があります。青森県の蕪嶋(かぶしま)神社ではクジラ汁を島根県の浜田市ではクジラ飯、山口権では「尾羽毛(おばけ)」という鯨の尾ひれを水にさらしたもの、また長野県ではクジラの小腸の輪切りを食べられていました。
・大阪の河内のあたりでは白みそ仕立ての干した蕪の味噌汁にしてその年の健康や災いが起こらない事を願って食べていました。
最後に
皆さんのご家庭ではどんな節分をお過ごしになるのでしょう?次の節分では今回紹介したこれまで自分の家では行っていなかったようなことを取り入れて新たな「我が家の節分」を作っても良いと思います。
また、「ここしばらく節分を行っていないなぁ」というお宅はぜひ、節分を復活させましょう。鬼滅の大豆で邪気を払い、1年間の無病息災を願いましょう。