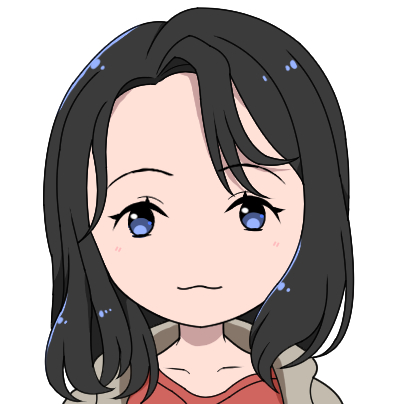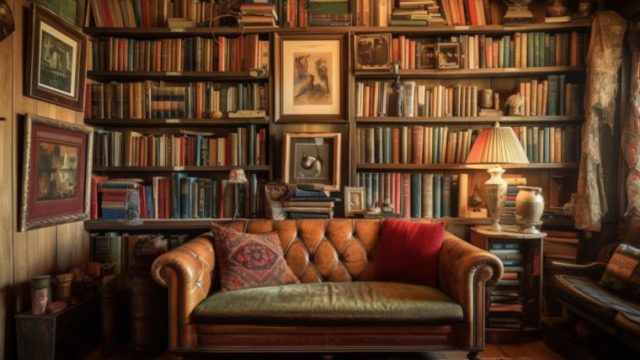冬の訪れは、自然が静寂に包まれ、澄んだ空気が私たちの心を引き締める季節です。白く輝く雪景色、凛とした冷たい風、そして暖かな灯火がもたらす安らぎ。冬は、一年の終わりと新たな始まりを告げる特別な季節です。
そんな冬には美しさや情感を表現するための季語が数多く存在し、その一つ一つに深い意味と豊かな情景が込められています。今回は、冬の美しい季語をテーマに、年の終わりと始まりを彩る言葉たちをご紹介します。
冬の季語には、厳しい寒さの中にも心温まる風景があり、それぞれの言葉が持つ意味や背景を知ることで、冬の楽しみが一層深まることでしょう。ぜひ、最後まで読んでみてくださいね。
冬将軍

「冬将軍」とは、とても厳しい冬の寒さを擬人化した言葉です。日本の気象庁が定義した言葉ではありませんが、日本では一般的に「シベリア高気圧」を表す言葉として使用されています。では冬将軍の言葉の由来はどこなのかというと、19世紀のナポレオンの逸話が元になっています。
ナポレオンがロシアに攻め込もうとした際、厳しい冬の寒さに多くの仲間が命を落としたため、撤退を余儀なくされました。それをイギリスの新聞が「ナポレオンが冬将軍に負けた」と表現したことから、冬将軍という言葉が生まれたのです。
そんな冬の厳しい寒さをなぞらえた俳句も数多く存在します。乾いた空気としんしんと降る儚い雪景色だけでなく、時に残酷な顔を見せる自然を表す季語として、ピッタリの言葉ではないでしょうか?
天気予報でもよく冬将軍という単語は耳にしますね。
霜の声

霜(しも) の降りた夜が冷たくしんしんと更けゆく様子を「霜の声」といいます。霜は晴れた寒夜に空気中の水蒸気が冷え、地面や植物などの者に触れてそのまま表面に付着した氷のことを指しますが、「しんしん」と音が鳴ったりはしませんよね。
あるはずのない音や声が聞こえるように感じるほど、静寂な寒い夜。そこにしっとりと積もる霜の様子に、「しんしん」とした冬の気配を感じる、というとても風情のある季語なのですね。
寒い夜の次の日に、薄く張った氷はどこか儚げな様子を感じさせます。
三寒四温

「三寒四温」とは、冬に起こる寒暖の周期のことを指します。晩秋から初春にかけて、中国北東部などで3日間ほど寒い日が続き、次の4日間くらい暖かい日が続くのが繰り返される気象現象に由来したものです。
『寒暖を繰り返し、次第に暖かくなっていく』という意味があることから、冬が明け、暖かな春がやってくる陽気さを感じる季語でもあります。現代では、「三寒四温のこの頃、どうぞご自愛ください。」など、気温の変化に対して、相手の体調を気遣う用途として手紙で使われることが多いです。
気温の変化が激しいと、風邪をひきやすいですよね…。
冬紅葉

冬なのに紅葉?と思った方もいるかもしれません。実際に「紅葉」は秋の季語ですが、冬になってから色付く葉の様子を「冬紅葉」といいます。主に庭園や神社などで見ることができるとされています。
冬の枯れた空気を色付ける紅葉に、真っ白な雪が降り積もる景色は、色の対比も相まって、紅葉の赤黄色を美しく鮮烈に印象付けます。冬でしか見られない違った衣をまとった紅葉を見かけた際は、一度立ち止まって眺めてみるのもいいかもしれませんね。
白に真っ赤な紅葉は、想像しただけでも印象深いですね。
冬萌

冬の暖かい日に木や草の芽が出ている様子を「冬萌」といいます。秋が過ぎ、葉を落とした木々達も、しっかりと冬に備えて栄養を蓄え、冬を越します。冬の間にも植物たちは着実に成長を続けているのですね。
降り積もった雪の間から除く緑色の新芽は、新たな希望やその兆しを予感させてくれます。冬萌はれっきとした冬の季語ですが、朗らかで温かみのある言葉なのですね。
冬萌を表す有名な植物だと、フキノトウなどがあげられます。
六花

「六花」とは雪の別名で、「りっか」「むつのはな」と読みます。雪は拡大すると六角形の結晶になっているので、この呼び名が生まれました。寒い地方は空気が乾いて大気中の不純物が少ないため、肉眼で六花を見た方も多いのではないでしょうか?
まるで花が咲いたような美しい形の結晶を初めて発見したのは中谷宇吉郎という大学教授で、彼は世界で初めて人工的に雪の結晶を作りだすことに成功した偉大な方です。中谷教授は「雪は天から送られた手紙である」という言葉を残しています。
雪の結晶の神秘に魅せられ、偉業を成し遂げた方がいたのですね。
さいごに
冬の季語には、寒さの中に隠れた温かさや、新しい年への希望が込められています。今回ご紹介した言葉を通じて、冬の魅力を再発見し、季節の移り変わりをより深く感じ取っていただけたでしょうか?これらの美しい季語を通じて、冬の情景を心に刻みながら、この季節を豊かに過ごしていただければと思います。
冬の寒さの中にも、温かさや美しさが溢れています。その一つ一つの瞬間を大切にしながら、日々を楽しんでください。言葉の持つ力や美しさを通じて、季節の彩りを感じ、心豊かな時間を過ごしていただければ幸いです。