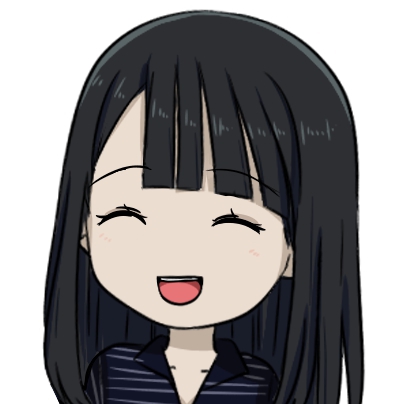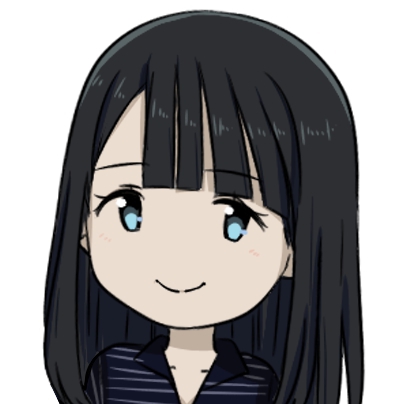春になると必ずといっていいほど、登場する限定味が「さくら」。みなさんは、さくら味の正体を知っていますか?さくら味は、さくらの花びらが一切使われていません。その正体はさくらの葉にありました。
この記事では、さくら味とは何なのか?どんな桜が使われているのか?和菓子などに使われている花は桜なのか?さくら味について解説していきます。
また、さくらの和菓子で代表的なのが「桜餅」です。「桜餅」には「関東風」と「関西風」がありました。どんな違いがあるのでしょうか?そちらについても詳しくご紹介します。この記事を読んで、お花見の話題にしてみてください。
目次
さくら味とは

さくら味とは、桜の葉から抽出される成分「クマリン」の香りのことをいいます。桜の葉を嗅いでも、さくらの香りはしません。桜の葉を塩漬けしたり、乾燥させたりすると香りが抽出されます。その香りこそが私たちの馴染みがある「さくら味」です。
タイトルにあった正体は桜の葉です!
さくら味で使われている桜は「オオシマザクラ」

さくら味で使われている桜はオオシマザクラ(大島桜)という花です。代表的な桜「ソメイヨシノ」には「クマリン」の抽出が難しいといわれています。それに比べ、オオシマザクラは「クマリン」が多く含まれており、抽出もしやすいためオオシマザクラが主に使われているのです。
オオシマザクラの特徴
オオシマザクラの特徴をご紹介します。オオシマザクラは伊豆大島原産の花で、白い花びらが特徴です。ソメイヨシノを香っても桜の香りはしませんが、オオシマザクラは香りがします。
オオシマザクラの花言葉は「純潔」「心の美しさ」です!
和菓子などに使用される花びらは「八重桜」

和菓子などに「桜の花びら」が乗っているのをみたことはありませんか?この花びらも「ソメイヨシノ」ではありません。花びらには「八重桜」という花びらが何重にもなった花が使用されています。
八重桜という品種は存在しない
八重桜という品種は存在しません。八重桜とは花びらが重なって咲く桜の総称をさします。桜の場合20枚以上の花びらを付ける品種を「八重桜」と呼びます。
八重桜の特徴
「ソメイヨシノ」や「山桜」などの一重桜と呼ばれる花びらが5枚ついた花は儚く、しなやかに見えます。それに対して八重桜の特徴はボリュームが多い花びらから華やかに見えることです。
お菓子で使用される、さくら味は「桜葉エキスパウダー」

お菓子などの食べ物で使用される「さくら味」は「桜葉エキスパウダー」を使うことが一般的です。「桜葉エキスパウダー」とは、桜の葉を塩漬けし、さらに塩抜きして、乾燥させたパウダーのことです。
桜葉の成分「クマリン」の効果

さくら味の成分「クマリン」には人への健康効果があります。代表的な効果を2つご紹介します。
むくみ改善
「クマリン」には血流の流れを良くする効果があります。血流の流れがよくなることで、むくみが改善されます。
風邪予防
「クマリン」には体内の細菌の増殖、生育を防止する抗菌効果があります。細菌の増殖、生育を防止することで、風邪予防に繋がります。
さくら味で代表的なお菓子は「桜餅」

さくら味で代表的なお菓子といえば「桜餅」です。「桜餅」とは色粉(いろこ)で色付けした小麦粉やお米の生地に餡子を入れ、さらに生地を桜の葉で巻いた和菓子のことです。「桜餅」は生地に小麦粉を使用した「関東風」と、生地にもち米などのお米を使用した「関西風」があります。これから詳しく解説します。
色粉は食品を色付けするものです!
関東風桜餅

関東風の桜餅は餡子をクレープのように小麦粉を原料とした皮で包み、その皮に桜の葉で巻いたものをいいます。東京墨田区にある寺「長命寺(ちょうめいじ)」の門番がお寺の門前で売り出したことから別名「長命寺餅」と呼ばれています。
関西風桜餅

関西風の桜餅は道明寺粉(どうみょうじこ)と呼ばれる、もち米を蒸して、乾燥させ粗挽きにした粉を生地に使用しています。餡子を道明寺粉で作った生地で包み、その生地を桜の葉で巻いたものをいいます。大阪府藤井寺市にある寺「道明寺」で始めて桜餅が作られたことから別名「道明寺餅」と呼ばれています。
まとめ
いかがでしたか?さくら味に関する知識を理解できましたか?スーパーやコンビニなどで販売される、さくら味のお菓子には原材料のところに「桜の花エキス」「桜葉パウダー」といった記載がされています。ぜひ、チェックしてみてください。
最後にご紹介した「桜餅」の「関東風」と「関西風」は2022年にウェザーニュースが調査した結果、全国的には「関西風」の「桜餅」が多いことが分かりました。
あなたの住んでいる地域や出身地の「桜餅」は「関東風」ですか?「関西風」ですか?気になった方は「桜餅」を購入してみるのも楽しいかもしれませんね。最後までお読みいただきありがとうございました。
こちらの関連記事もご覧ください。