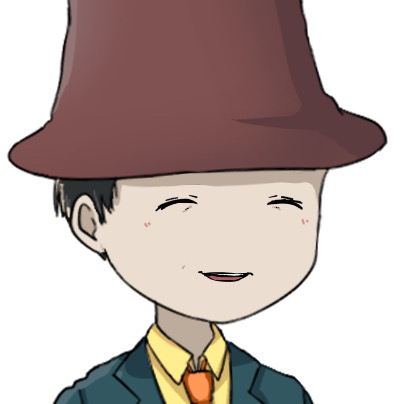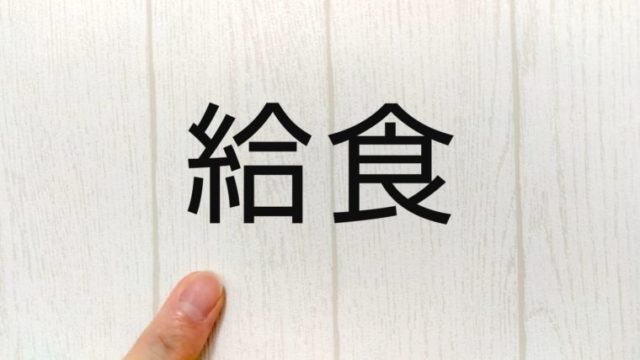あなたは紅茶や緑茶はよく飲みますか?紅茶と緑茶、どちらが好きで、どちらをよく飲まれるのでしょう・・・?
実は、紅茶も緑茶も同じ期の葉っぱから作られるのをご存知でしょうか?どちらも「チャノキ」という木の葉っぱを使って作られます(今回は取り上げませんがウーロン茶も「チャノキ」の葉っぱで作られます)。
同じ葉っぱなのにどうしてこんなに違う飲み物になるのでしょう?今回はそんな紅茶と緑茶の違いをご紹介します。作り方の違いから始まり、おいしい淹れ方の違い、味の違い、さらには合う食べ物の違いについての雑学をご紹介します。
目次
作られ方の違い・・・紅茶は発酵させます。

紅茶や緑茶は同じ「チャノキ」の葉っぱだとお伝えしましたが、それでは何が違うのでしょう。実は紅茶は発酵させます。
発酵というとヨーグルトやワインなどのお酒などで用いられるような酵母菌などの微生物を用いた「発酵」を思い浮かべる方もいらっしゃるかと思いますが。もちろんこれらヨーグルトやお酒も発酵です。
しかし、お茶の場合は発酵の意味が少し違います。お茶の発酵は微生物を用いた「発酵」ではありません。お茶の葉っぱを酸化させることを「発酵」といいます。チャノキの葉っぱにもともと含まれている酵素によって、チャノキの葉っぱに含まれるカテキンを酸化させることをお茶の場合「発酵」といいます。
チャノキの葉は放っておくと(皮をむいたりんごが茶色に変色していくように)どんどん中に含まれる成分(カテキン)が酸化していきます。緑茶はこの発酵(変色)を抑えるために葉っぱの収穫後に蒸して、緑色を保ったものです。
逆に紅茶はチャノキの葉を摘んだあと、茶色くなるまで放っておきます(発酵させます)。
緑茶のように発酵をしないように処理するお茶を「不発酵茶」、紅茶のように茶色になるまで発酵させるお茶を「完全発酵茶」と言います。また、ウーロン茶は途中で発酵を止めるので「半発酵茶」と呼ばれます。
おいしい味の違い

それではここからはそれぞれのお茶の「美味しい(と言われる)味」の違いをお伝えします。
一般的においしい緑茶とは渋みが抑えられていてかつ、アミノ酸などの甘みを感じることができるお茶を言いますよね。
こういった緑茶に出会った方は少ないかもしれませんね。
ではおいしい紅茶とはどんな紅茶だと思いますか?実は緑茶とは違い渋み(ワインの雑学でもでえきた「タンニン」)も大切な要素となります。渋みや香りが引き立つようなものが「おいしい紅茶」と言われて言います。
紅茶っていろんな地域の名前がついた種類がありますよね。実は緑茶も産地や製法により味が異なります。
「私はダージリンが好き!」とか紅茶の好きな産地がある方、好きな緑茶の産地もぜひ作っていただきたいです。
ちなみにチャノキは世界各国で作られていますが、チャノキが栽培されているのは北緯45度(北海道の利尻島のすぐ南)から南緯35度(ニュージーランドの北端あたり)くらいの地域です。その中で緑茶をよく飲む国は・・・(1人当たりの緑茶消費量順で)日本、ベトナム、中国、インドネシア・・・です。
やはり日本人が一番緑茶を飲んでいますよね。
中国はウーロン茶というイメージを持っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?中国でも緑茶も飲まれています。
淹れ方の違い

「お茶なんかお湯を注げばいい!」なんて考えている方は損していますよ。同じ茶葉でも淹れ方により味も風味も変わってきます。ここでは緑茶と紅茶の「おいしい淹れ方」を比較してみましょう。
緑茶のおいしい淹れ方 ― 70℃のお湯
緑茶は熱湯で淹れると渋み成分のカテキンがたくさん出てくるので渋くなります。だから60~70℃までお湯を冷まして淹れます。
1、熱いお湯を湯のみ茶わんに注ぎ、茶わんを温めながらお湯を冷まします。
2、急須に茶葉を入れ、1で湯飲み茶わんに注いだお湯を急須に入れます。
3、茶葉が開くまで1分ほど待ちます。
4,急須から湯飲み茶わんに注ぎます(2個以上の茶碗に1度に注ぐ場合は均等の濃さになるように少しずつお茶を注いでいきます)。
紅茶の美味しい淹れ方 ― 95℃以上で淹れる
紅茶は渋みもおいしさの1つでしたよね。タンニンなどの渋み成分は95℃以上でないと出てきません。逆に温度が低いとカフェインがばかり出てきます。カフェインは80℃くらいから出てきて、エグミが強くなります。だから沸騰したお湯で紅茶は淹れます。
1、 ティーポットにお湯を注ぎ、温めておきます。
2、 ティーポットのお湯を捨て、茶葉を入れて熱湯を注ぎます。
3、 ティーカップに均一な濃さになるように注ぎます。
緑茶は70℃で、紅茶は95℃以上のお湯で淹れるとおいしくなります。
ちょっとティータイム~ティバッグでのおいしい紅茶の淹れ方
先ほどティーポットでの紅茶の淹れ方をご紹介しましたが、ティーポットで紅茶を淹れる方はよっぽど紅茶が好きで、いつも飲むような方だと思います。時々しか飲まない方はティーバッグで淹れることが多いんじゃないでしょうか?そこでここではティーバッグでの紅茶のおいしい淹れ方をご紹介します。
1、ティーカップにお湯を注ぎ、カップを温めます。
2、ティーバッグを指で広げ、かつ、中の茶葉をほぐします。
3、1カップのお湯を捨て、ティーバッグを入れます。
4、お湯を注ぎ、蓋をして蒸らします。
5、1~5分後、ティーバッグを引き上げます。その時に軽くティーバッグを揺らして濃さを均一にし、カップからとり出します。
ティーバッグはむやみに揺すらないようにします。じっと溶け出るまで待ちましょう。
それぞれのお茶に合う食べ物

元となる葉っぱは同じでも、作られ方、味、淹れ方の違いをご紹介しました。ここからはどんな食べ物が合うかをご紹介します。
紅茶に合う食べ物
紅茶に合う食べ物と言えばお菓子類でしょうかね。ケーキ、ビスケット、アイスや、ドライフルーツ、チーズなどにも合います。
また、紅茶には砂糖やジャム、ミルクやブランデーを入れて飲むこともありますよね
緑茶に合う食べ物
紅茶にはお菓子類が合うとお伝えしましたが、緑茶も和菓子など甘い物にも合いますよね。さらに、煎餅を食べる時に緑茶を飲みたくなることありませんか?緑茶の場合は甘い物のみならず塩味の利いたもの、例えば梅干しなどの漬物や塩昆布などにも合います。また、お寿司屋さんで「上がり」や、お茶漬けにも緑茶を使います。
緑茶は今でこそ「緑茶ラテ」といった飲み方をすることもありますが、普通はそのままストレートで飲みますよね
最後に・・・
ここまで違うところばかりご紹介しました。しかし同じチャノキの葉っぱから作られる2つの飲み物です。つまり親が同じなので兄弟ですから似ているところもあります。それはそれぞれの茶葉に含まれる成分です。どちらも渋み成分のカテキンやリラックス効果を持つデアニン、またカフェインなどを含んでいます。
甘いジュースを購入するのであれば、緑茶や紅茶のいろんな産地の茶葉を購入して楽しんでみてください。また、いろんな産地の茶葉をブレンドするのも楽しいと思います。
あなたお好みの紅茶、緑茶の飲み方がありましたら、ぜひ教えてください。