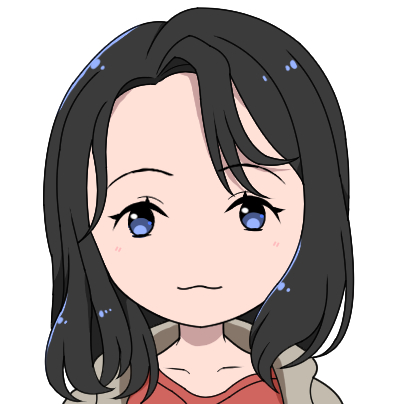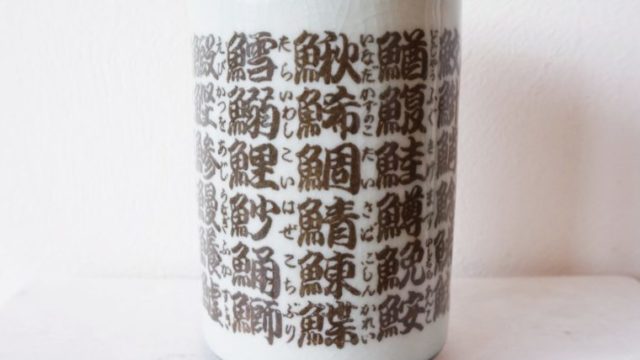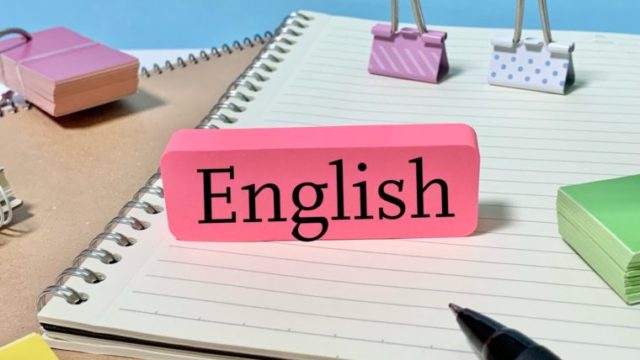春は、自然が目覚め、新たな命が芽吹く季節です。桜の花びらが風に舞い散る桜吹雪、朝日に輝く朝顔の花、そして春風に舞う胡蝶の姿―そんな可憐な風景が、春の訪れを感じさせてくれます。しかし春にまつわる言葉には、それだけではない意外な一面があり、時に深い哲学や文化が込められているのです。
そんな春にまつわるかわいい言葉の中には、意外性を秘めたものも多くあります。季節の移り変わりや自然の美しさを感じさせる一方で、人々の心にさまざまな思いを呼び起こします。この記事では、そんな春の言葉の一部を紹介しますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
桜

春といえば桜ですよね。俳句では「花」は「桜」を指しているほど古来から桜は花の代名詞として日本で愛されてきました。かつては桜ではなく梅がその立場をあらわしていたとされていますが、時代が流れ、花見などの風習や行事を経て、花といえば桜、と呼ばれるまでになりました。
季語も多数存在し、桜を使った俳句も数多く生まれ続けています。『さまざまの事おもひ出す桜かな』という松尾芭蕉の句があり、故郷を訪れた松尾芭蕉が、咲いている桜を見てかつて仕えた君主のことを思い出した際に詠んだとされています。
美しくもあり、可憐な言葉の象徴ともいえるでしょう。
春眠

その名の通り、春の眠りを指す言葉です。『春眠暁を覚えず』ということわざがあるように、春の夜は温かくて寝心地がよく、夜が明けてもなかなか目を覚ますことができない、という少しおっとりとした言葉ですね。
似た言葉で「春眠し」もありますが、こちらは春の温かさに睡魔が誘われて眠りこけてしまうことを指す言葉だそうです。春のうららかな陽気をあらわす、おだやかさを感じますね。
春はあたたかくて過ごしやすいので、ついうとうとしてしまいますね。
花の便り

花が咲いたことを知らせる言葉です。桜の解説にもあったように「花」は「桜」を指す言葉として用いられていたので、桜が咲いたことを伝える意味でもあります。古くから俳句の季語に多く用いられており、現代でも手紙における冒頭の文章に「花便りも伝わる今日このごろです。」など時候の挨拶として使われています。
ひとつの世間話の導入として、やわらかくあたたかな印象を感じますね。
桜が咲いたことを知らせる言葉には、ロマンチックな風情がありますね。
雀の子

1年中目にする雀がなぜ春の言葉?と思う方もいるかもしれません。雀は3月~4月にかけて卵を産み、春に雛として過ごすのです。日本の初物をありがたがる風習も相まって、おめでたいものの象徴として春の言葉に用いられています。
雀は人の住むところに巣を作り、卵を産み雛がかえり、親鳥と人間に見守られながら成長していきます。そんな光景も春のやわらかな雰囲気にぴったりですね。
松尾芭蕉も「雀子と声鳴きかはす鼠の巣」という句を詠んでいます。
石鹸玉

「石鹸玉」は「しゃぼんだま」と読みます。石鹸玉が春の言葉である理由は、春に子供達が外に出て、風を受けながらする遊び…というイメージから来ています。石鹸玉16世紀ごろから存在し、江戸時代の日本では、行商人が春や夏にかけて石鹸玉を吹きながらやってくる光景がしばしば絵画にも残されています。
ですが、石鹸玉が春の言葉として登録されたのは1900年ごろなので、江戸時代の行商人の光景ではなく、子供たちが春に石鹸玉を吹いて遊ぶというイメージが由来としてふさわしいでしょう。
石鹸玉は見ていると和やかな気持ちになりますね。
鞦韆

「鞦韆」は「しゅうせん」と読みます。「しゅうせん」ってなに?と思われるかもしれませんが、「しゅうせん」は「ブランコ」のことです。遊具のブランコが春の言葉である理由は、実はブランコは現代日本の遊びでなく、本来は古代の中国の習慣が元になっています。
古代の中国では、冬至から105日後に訪れる「寒食節」に、女性が鞦韆で遊ぶ習慣がありました。春の訪れを祝う儀礼の一環として、鞦韆は春の言葉となったのです。
ブランコ遊びは中国にもあったのですね。
さいごに
春の可愛らしい言葉には、季節の美しさや喜びが詰まっています。桜の花が咲き誇り、鳥たちがさえずり、新緑が木々を包み込む春の風景は、私たちに暖かな感動を与えてくれます。しかし、その美しい言葉や風景の裏には、時には切なさや哀愁も潜んでいます。
桜吹雪の儚さや、花鳥風月の静けさに込められた人間の心情―そんな意外な一面も春の言葉にはあります。春は新しい始まりの季節でもあります。春の言葉たちが私たちの心を豊かにし、春の訪れをより一層楽しませてくれることでしょう。