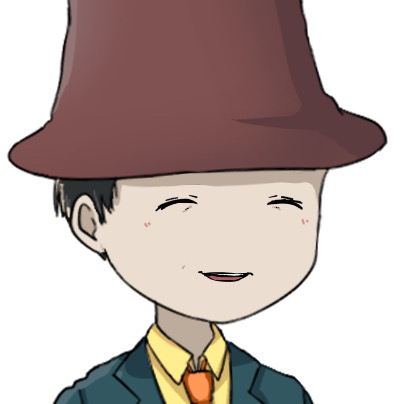暑い夏みなさんも、のど越しの良い寒天やゼリーを無性に食べたくなることがありませんか?あなたは寒天とゼリーのどちらが好きですか?この2つ何が違うのでしょう?
実はゼリーは動物のコラーゲンから作られるのです。コラーゲンからできているゼリーのプルプル感はイメージできるかと思います。しかし寒天です。なんと海藻から作られているのです。海草ならば海沿いの地域で盛んに製造されていると思いきや、なんと海のない長野県や岐阜県で昔から作られています。
今回はこれら2つをはじめ、似たような形状の食べ物、ナタデココやタピオカ。さらにこんにゃくに至るまで、それぞれ何が固まるか(原材料)。製法や特徴を紹介します。
読めば誰かに話したくなること間違いなし!です。
目次
寒天

原材料
寒天の原材料はテングサ科やオゴノリ科の海草です。
作り方
寒天の素、材料寒天の製造法
お菓子として作られる寒天。ここではまずお菓子の素の寒天、材料としての寒天の製造方法を紹介します。材料寒天には形状により棒寒天、糸寒天、粉寒天などに分かれます。
- 原材料の海藻を煮て、寒天の成分を煮出します。
- 煮出した液を濾過。液を冷やして固めます(一度寒天として固めてしまうのです)。
- 2で固めたものを脱水します。材料寒天の形状により脱水方法には、プレスして脱水。凍らせて脱水させる凍結脱水の2つがあります。
- 最後に乾燥させ、材料の寒天が完成します。
海草から作られる材料寒天は「海なし県」である長野県や岐阜県で昔から作られてきました。いずれも内陸で冬の寒さが厳しく、乾燥する地域です。このような地域の露天で冬、凍結脱水されるのです。
寒天菓子の作り方
- 溶かす工程・水100mLに材料寒天を1~2gの割合で、かき混ぜながら中火にかけます。沸騰したら火を弱めて、1~2分で溶けます(溶ける時の温度は90℃以上と高めです)。
- 固める工程・容器に移し固めます。凝固温度は30~40℃。そのため冷蔵庫に入れなくても常温で固まります。
特徴
- 状態変化(固体→液体→固体→液体)が常温より高い温度で起こります。
材料寒天は90℃以上で液体に溶解します。
溶かした液は30~40℃で(常温でも)固まります。
一度固めたものは70℃以上で再び解けます。
そのため羊羹など冷蔵庫に入れなくても解けることがありません。
- 植物(海藻)由来の寒天。そのためパイナップルやキウイフルーツといったタンパク質分解酵素を含む果物を入れても固めることができます。
- 植物(海藻)からできている寒天。食物繊維を含んでいます。そのため便通をよくする効果があります。
またお米を炊くときに粉寒天を加えると血糖値を抑える効果があるという研究結果もあります。
ゼリー

原材料
ゼリーの原材料は牛や豚の骨や皮に含まれるコラーゲン(たんぱく質の一種)です。
作り方
ゼリーの材料、ゼラチンの製造法
ゼリーの素は粉ゼラチンです。
- 原材料から酸や石灰(せっかい)を用い、コラーゲンの成分「オセイン」を抽出します。
- オセインを洗浄後、50~60℃の温水でゼラチンを抽出します。
- ゼラチンを抽出した液、これを濾過・濃縮して、濃度を高めます。
- 高温で殺菌し、乾燥させた後、粉砕したら粉ゼラチンの完成です。
ゼリーの作り方
- 40~60℃に温めた液体(水やシロップ)100mLに粉ゼラチン2gの割合で加えて攪拌(かくはん)、溶かします。
- その後容器に移し、冷蔵庫で冷やして固めます。
特徴
- 状態変化の温度が寒天と比べて低い
粉ゼラチンは40~60℃で液体に溶けます。そのため(寒天のように火にかけた鍋を使わなくても)電子レンジで温めたシロップなどに溶かすことができます。
ゼラチンを溶かした液は20℃以下でないと固まりません。したがって冷蔵庫で冷やす必要があります。
固まったゼリーは25℃以上で解けます。そのため夏場など冷蔵庫に入れておく必要があります。
- コラーゲンはたんぱく質の一種です。キウイフルーツやパイナップルといったタンパク質分解酵素を含むものを入れると固まりません。
この他にタンパク質分解酵素はパパイア、イチジク、マンゴーなどにも含まれています。
また、グミもゼラチンで作られます。グミの場合は液体100mLにゼラチン10g。ゼリーの5倍のゼラチンを加えることで弾力が生まれています。
ナタデココ

原材料
ナタデココの原料はココナッツミルクです。
作り方
ココナッツミルクにナタ菌という酢酸菌の一種を加えて発酵。表面に固まった物がナタデココです。
ナタデココはスペイン語でnata de cocoと書きます。nataは液面にできる被膜、cocoはココナッツです。よって「ココナッツの被膜」という意味です。
タピオカ

原材料
タピオカの原料はトウダイグサ科イモノキ属・キャッサバにできる芋のデンプンです。
作り方
キャッサバの芋から取り出されたデンプンを水に溶かして加熱。回転させながら丸くし、乾燥させたものが白い「タピオカパール」です。茹でると食べられます。
日本でブームになったタピオカミルクティー。これに入っているものは黒色をしたブラックタピオカです。これはカラメル色素で着色したものです。
日本ではタピオカの代わりにこんにゃくが使われることも少なくないようです。
また、日本にもデンプンから作られるお菓子があります。「わらび餅」はわらびの根から。また「くず餅」はクズの根からそれぞれ採られたデンプンで作られます。
こんにゃく

こんにゃくゼリーやタピオカの代わりにも使われるこんにゃくについてご紹介します。
原材料
こんにゃくの原料はコンニャク芋です。シュウ酸カルシウムという毒を多く含んでいます。
作り方
- コンニャク芋を水に細かくすり下ろします。
- アルカリ(水酸化カルシウムなど)の凝固剤を加えます。
- 成形容器に入れ、20分ほどで固まります。
- 最後に茹でて完成です。
アルカリは凝固剤でもあり、毒を抜く効果もあります。昔は草木を燃やした後の灰。これを水に浸けた液を使っていました。
最後に
寒天とゼリーの違い、いかがでしたか?寒天は海草なので食物繊維を含みます。また、材料寒天を溶かすときも固まる時もゼリーより高い温度で起こりました。
ゼリーはコラーゲン。動物性のたんぱく質です。そのためタンパク質分解酵素を含むパイナップルやキウイフルーツを入れると固まりません。寒天より低い温度で「固体-液体」の変化を起こすので冷蔵庫で冷やす必要があります。
その他、ナタデココはココナッツミルクの発酵食品。タピオカ、わらび餅、くず餅はそれぞれのデンプン。さらにこんにゃくの毒を除くために昔は草木の灰液を使っていたこともお話ししました。
これら昔からある食べ物、昔の人はすごいですね。ぜひ今回紹介したことを他の人にも教えてあげてください。