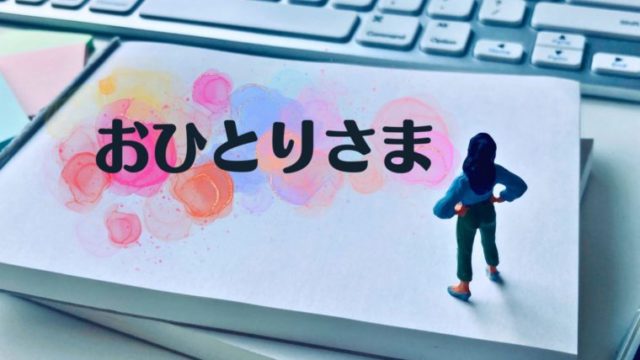皆さんは、夏と聞いたらどんなことを思い浮かべますか?海や山に遊びに行くことで、自然と触れ合う機会を作ることができます。親戚と会う楽しみがある人もいるかもしれません。やることも楽しみも多い夏という季節には、豆知識がたくさんあります。
夏の豆知識は、食べ物や文化、自然に関するものまでさまざまです。今回は、夏の豆知識を紹介します。風鈴のルーツやアサガオの秘密など、知っているようで知らない雑学も紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。
目次
食についての雑学

かき氷のシロップはみんな同じ味!?
かき氷は、夏祭りなどの屋台で食べることができます。「かき氷のシロップは全部同じ味だよ!」と言っている人に出会ったことはありますか?着色料と香料で、味が違うように感じるというのが理由です。視覚、嗅覚で舌が騙されているということになりますね。
しかし、どの会社も同じようにかき氷のシロップを作っているわけではありません。果汁や果肉が入ったちょっと贅沢なシロップも存在します。夏にお家でかき氷を楽しんでいる人は、ぜひチェックしてみてください。味の比較をするのも面白いかもしれませんね。
流しそうめんの始まり
流しそうめんは、夏の風物詩のひとつです。竹を伝ってくる水とそうめんは、見ているだけで涼しくなります。さらに、食べることもできるひと粒で二度おいしい文化です。野外でのパーティなどで楽しむのもいいですよね。
そんな、流しそうめんの発祥の地は九州地方です。流しそうめんは、昭和30年に宮崎県の高千穂町で生まれました。地元の人は、夏場に外仕事をする際そうめんを高千穂峡の冷水と竹で冷やしたといわれています。流しそうめんは、この様子を見て思いついた文化なのです。
考えた人はユーモアのセンスがありますね。
スイカは野菜?果物?
夏になると、冷えたスイカが食べたくなる人もいるのではないでしょうか。お行儀はよくないですが、種を飛ばして遊ぶのも楽しいですよね。そんなスイカは、果物ではなく野菜の一種だといわれています。
「おやつとして出されるのに…?」「果物売り場に売っているのに…?」このような理由で、スイカを果物だと思っている人もいるかもしれません。しかし、性質上スイカは野菜に該当します。スイカだけではなく、イチゴやメロンも同様の理由で野菜に分類されるのです。
それでも、取引の際は果物として分類され、食品成分表には果実類として記載されています。つまり、スイカは果物…というのも別に間違いではないということです。
冷たいものを食べることで、体を冷やすこともできます!夏だからこそおいしいと感じる食べ物もあるのではないでしょうか。次は、夏の文化にまつわる豆知識を紹介します。
文化の豆知識

風鈴は魔除けとして吊るされていた
風鈴は夏の風物詩のひとつです。音色を聴くと、暑い夏が少し涼しくなったようにも思えます。この風鈴は、中国から日本に伝わりました。風鈴のもととなったのは中国の「占風鐸(せんぷうたく)」という占いの道具です。唐の時代は、風向きや音の鳴り方で政治判断などを行いました。銅でできている風鐸は、音も風鈴より鈍かったといわれています。
そして、平安時代では魔除けとして吊るされていました。この頃から「風鈴」と呼ばれるようになります。江戸時代には、西洋との貿易を通して日本にガラスの文化が広まりました。その頃にできたのがガラスの風鈴です。
しかし、ガラスがまだ希少な時代だったので、当時の風鈴は今よりもずっと高価な物でした。そんな風鈴も、今では百円ショップで購入できるようになっています。これもちょっと面白い話ですよね。
お盆のお供え物にキュウリとナスを置く理由
お盆は、私たちのご先祖が一時的に帰ってくるという重要な行事です。お盆と聞いたら、キュウリとナスを連想する人も多いのではないでしょうか。お盆にはキュウリとナスを食べるから…というわけではありませんよね。
キュウリとナスに、木の棒などを4本刺して作るあの置物を思い出します。では、あの置物は何のためにあるものなのでしょうか。4つの足がついたキュウリは馬、ナスは牛にみたてて作られています。
これらは「精霊馬(しょうりょううま・しょうりょううし)」というお供え物です。馬といえば足が速い生き物ですよね。キュウリの馬には「早く戻ってきますように」という願いが込められています。
反対に、ナスの牛は「帰るのが少しでも遅くなりますように」という意味です。これは、ゆっくり歩く牛にちなんで考えられています。長く一緒にいたいという気持ちがこもっていますね。しかし、地方によっては反対になることもあるようです。
その場合は「ゆっくり丁寧にお迎えする」という意味でナスを置き「早く休んでほしい」という意味でキュウリを置きます。これはこれで、ご先祖への気遣いが感じられて素敵ですね。
ちなみに、夏野菜の収穫を報告するという意味もあります。どちらも歴史ある夏の豆知識ですね!
生物に関する豆知識

ホタルは日本に50種類いる
夏にホタルを見に行ったことはありますか?筆者は子供のころに見にいきました。虫が光っていることが信じられなかったです。そんなホタルは、世界に2000種類いるといわれています。そして、日本にいるホタルは50種類です。
「日本ですらそんなにいるイメージがない…」と思った人は、正しいのかもしれません。なぜなら、成虫になってから光るホタルばかりではないからです。幼虫のみが光るというタイプもいます。
少し脱線してしまいましたが、日本には意外と多くのホタルが生息しているのです。
アサガオの開花と日没時間の関係
夏休みに、アサガオの観察をしたことがあるという人もいるのではないでしょうか。朝早くに開花して昼には萎んでしまうため、アサガオという名前がつきました。朝早くに咲くので「日の出の時間に合わせて咲くのだろう」と思っていませんか?
実はそれは間違いで、アサガオは日没の時間によって開花時間が決まります。アサガオは、日没後10時間で開花するというのが正解です。秋になると日没は早くなるので、アサガオの開花時間も深夜に近づきます。以上が、アサガオと日没の意外な関係です。
まじめにアサガオを観察した人であれば、すでに知っているのかもしれませんね。
蚊の漢字はなぜ「虫」に「文」?
夏になると現れる虫「蚊」は、私たち人間や動物に様々なストレスを与えます。耳元で不快な羽音を響かせるだけではなく、かきむしりたくなるほどかゆい腫物を作って逃げていくのです。そんな蚊は、漢字で書くとき「虫」に「文」と書きます。
では、一体どうして「蚊」はこのような漢字になったのでしょうか?この漢字は中国で誕生しました。かつての中国で「文」は「ミィウェン」と発音されたといわれています。その「文」の発音が、蚊の羽音と似ていたことから漢字の「蚊」が誕生しました。
意味ではなく音が由来だったなんて意外ですね。
夏は、いろいろな虫に出会うことができます。蚊とはあまり出会いたくないですね。刺されないためにも対策をして出かけましょう!
さいごに
以上、夏の豆知識を紹介しました。夏はおいしい食べ物がたくさんあります。流しそうめんを冬にやってみると、面白くないと感じるかもしれません。スイカも、かき氷もおいしいとは感じられないのではないでしょうか?どれも、暑い夏だからこそ楽しめる食文化ですね。
今では簡単に手に入ってしまう風鈴ですが、自分で絵付け出来るものも売っています。自分だけの風鈴を作ってみるのも素敵です。夏は楽しいことがたくさんあるので、大人になってからでも自由研究をしてみてはどうでしょうか?
夏の雑学について調べてみるのも面白いですね。