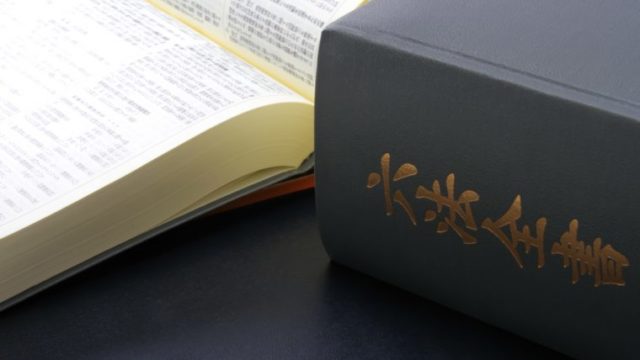皆さんが一番うれしい月(month)は何月でしょう。ゴールデンウィークがある4月~5月にかけて?それともシルバーウィークがある9月でしょうか?それでは逆にやる気が出ないのは・・・祝日が全くない6月や12月でしょうか・・・
(お仕事によっては不定休の方もいらっしゃるかもしれませんが)毎週日曜日に休みがあるのに、カレンダーのウィークデーに赤色の数字があるとわくわくしますよね。今回はそんな赤色の数字の日についての雑学です。
皆さんは祝日、祭日、休日の違い、ご存知ですか?法律で祝日や休日が決められていますがそれぞれどんな違いがあって、個々のお休みにはどんな意味があるのかをご紹介します。
祝日とは・・・1948年に大きく変わりました

でははじめに「祝日」についてお話しします。「祝日」は1948年7月20日に大きく変わりました。というのもそれまで大正元年に公布された祝祭日に関する勅令(ちょくれい・天皇陛下の命令)「休日ニ関スル件(きゅうじつにかんするけん)」に従っていましたが、1948年7月20日に新たなに「国民の祝日に関する法律」が使われ始めたからです。
勘のいい方はわかるかと思います。これは戦後の日本がポツダム宣言を受け入れて行われたGHQ(連合国軍最高司令部)による改革の一つです。
ここで大きく変わったことは「祭日」という言葉がなくなったことです。つまり現在の法律にはそれまではあった「祭日」はなくなり、すべて「祝日(または休日)」となりました。祝日を正式には「国民の祝日」と言います。
「祭日」は・・・なくなりました

祭日はなくなったとお伝えしましたが、1948年7月19日以前の勅令にあった「祭日」とは皇室で祭事(さいじ)が行われる日で、宗教色のある日でした。
全部で祭日は11日ありました。そのうち6日は現在も名前を変えて祝日として残っています。ここからは これら11個の祭日についてどんな日だったのか簡単に見ていきましょう。
祭日だったが名前を変えて残っている祝日
はじめに皇室で祭事が行われていた祭日のうち「名前は変わってしまいましたが現在も祝日としてお休みになっている日」ご紹介していきます。以下の6つの祝日がこれにあたります。
元日(1月1日)は四方節だった
1月1日は天皇が早朝、天と地の四方の神々にお祈りをする日で、四方節と呼ばれていました。
現在は一年の始まりをお祝いする日ですよね
ちょっとブレイク ~ 元日と元旦の違い・・・

皆さんは1月1日を「元日」と言ったり「元旦」と言ったりしますよ?この2つの違い、ご存知でしょうか?この違いは意外と簡単です。違いは「日」と「旦」ですよね。
実は「旦」という字は夜明けをさします。「旦」の字をばらすと「一」と「日」ですよね。地平線(一)から太陽(日)が昇ってくるように見えてきませんか?だから「元旦」は「1月1日の早朝(夜明け)」を表します。
建国記念日(2月11日)は紀元節(きげんせつ)だった
古事記や日本書紀で日本最初の天皇陛下とだと記される神武(じんむ)天皇が即位した日として1873年(明治6年)に定められました。
春分の日(3月20~21日)は春季皇霊祭(しゅんきこれいさい)、秋分の日(9月22~23日)は秋季皇霊祭(しゅうきこれいさい)だった
お彼岸であるこれらの日は歴代の天皇陛下や皇后陛下などの霊を祭る日でした。
勤労感謝の日(11月23日)は新嘗祭(にいなめさい)だった
天皇陛下がその年にとれたお米などの穀物を神様(宮中三殿のうちの神嘉殿(しんかでん))に奉納する日でした。
文化の日(11月3日)は明治節(めいじせつ)だった
明治天皇の誕生日である11月3日は明治天皇に遺徳(いとく)をしのんで制定されていました。
なくなってしまった祭日
ここまでは現在も休みの日として残っている(旧)祭日についてご紹介しましたが、ここからは法律制定により休みではなくなってしまった、以前は祭日だった日について紹介します。
元始祭(げんしさい・1月3日)
天皇の始まりをお祝いする日でした。
新年宴会(しんねんえんかい・1月5日)
奈良時代から宮中では行われていたのですが、室町時代に行われなくなり、明治に復活した新年をお祝いする行事です。皇族の方々や、軍幹部、官僚や各国の大使などを招いての宴会が開かれていました。元日は何かと忙しいので5日だったようです。
神武天皇祭(じんむてんのうさい・4月3日)
初代天皇の神武天皇が崩御(ほうぎょ・亡くなった)された日です。
神嘗祭(かんなめさい・10月1日)
(新嘗祭は宮中の神嘉殿にその年のお米など穀物をお供えしたのに対し)伊勢神宮の天照大神(あまてらすおおみかみ)にその年初めて取れた穀物(初穂・はつほ)をお供えする日でした。
大正天皇祭(たいしょうてんのうさい・12月25日)
大正天皇が崩御された日で、大正天皇をしのんで設けられました。
そのほかの祝日

ここまでは以前の勅令で「祭日」だった日について紹介してきました。ここからはそのほかの現在の祝日についてご紹介します。
成人の日(1月第2月曜日)
奈良時代以降、小正月である1月15日に元服(げんぷく)の儀(大人になる儀式)が行われていました。
それが1948年の法律で「成人の日」と改められます。
1998年、1月15日に大学入試センター試験が重なる年が出てくることなどの理由から法律改正。ハッピーマンデー制度が導入され、2000年からは1月の第2月曜日が成人の日になりました。
もう1月15日が成人の日になることがなくなってしまいました。
法律には成人の日のことを「おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます」ための日と記されています。
天皇誕生日(2月23日)
令和天皇の誕生日です。
昭和の日(4月29日)
昭和天皇の誕生日です。2006年までは「みどりの日」でしたが2007年より「昭和の日」に変わりました。
憲法記念日(5月3日)
1947年5月3日に現在の日本国憲法が施行(しこう)されたことをお祝いする日。
みどりの日(5月4日)
(2006年までは4月29日だった)みどりの日は2007年に5月3日の建国記念日と5月5日の子供の日の間を埋めるように5月4日に移動され、ゴールデンウィークを構成する3連休なりました。
ちょっとブレイク~ゴールデンウィークの名前の由来・映画館が大繁盛したから

4月後半くらいになると、「今年のゴールデンウィークは最長〇連休の企業があるってニュースで話してたよ。」など話題になる職場もあると思います。皆さんはこの「ゴールデンウィーク」という言葉がどのようにできたかご存知ですか?
実はこの言葉は映画会社の宣伝文句だったのです。1951年(昭和26年)のこの連休中に上映された「自由学校」という映画。この映画がお正月やお盆の時期の映画よりもヒットしたと言います。
そこで毎年この連休期間に映画をたくさん見てもらおうと考えた映画会社の専務。(「ゴールデンタイム」になぞらえて)宣伝用語として「黄金週間(ゴールデンウィーク)」と呼ぶようにしたのがきっかけです。
宣伝用語なのでNHKなどメディアでは現在でもゴールデンウィークとは言わずに「春の大型連休」と言っているのはこのためです。
こどもの日(5月5日)
こどもの日を法律では「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」日とされています。
海の日(7月第3月曜日)
1996年からあります。当初は7月20日でしたが、ハッピーマンデー制度により2003年からは7月第3月曜日に変更されました。「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う」目的で制定されました。
山の日(8月11日)とは
2014年(平成26年)に作られた祝日です。「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを目的に制定されました。
敬老の日(9月第3月曜日)
敬老の日も2002年(平成14年)までは9月15日でしたが、2003年(平成15年)よりハッピーマンデー制度により9月の第3月曜日へと変更されました。「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う」ことを目的に制定されました。
スポーツの日(10月第2月曜日)
1964年(昭和39年)10月10日に東京オリンピックの開会式が行われたことを記念して1966年(昭和41年)にスポーツの振興を願って「体育の日」が10月10日に作られました。
2000年(平成12年)にハッピーマンデー制度により体育の日は10月10日から10月第2月曜日に変更されます。
2020年に「体育」という言葉より広い意味を持つ「スポーツの日」へと名前が変えられます。法律上の目的も体育の日では「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」だったのが、「スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う」へと変更されました。
休日とは

休日とは読んで字のごとく「休みの日」ですよね。これも法律で3種類あります。
1.ここまで話してきた「国民の祝日」
2.日曜日と国民の祝日が重なったときに次の日を休みにする「振替休日」
3.祝日と祝日のあいだに1日だけ平日がある場合休みとする「国民の休日」
です。3の国民の休日は「9月の第3月曜日の敬老の日」と「22または23日の秋分の日」の間で起こることがあります。秋分の日が水曜日になる年に発生します。最近では2015年、今後は2026年、2032年、2037年に国民の休日が出てきます。
さいごに・・・・
今回は「カレンダーのウィークデーにあると嬉しい赤色の数字の日」についてお伝えしました。「休みだからうれしい!」だけではなく、それぞれいろんな意味が込められていることが分かっていただけたでしょうか。
そういえば私が小さい頃((昭和の終わりごろ))でも、祝日には玄関に国旗を掲げていた家もありましたよ
でもあなたにとってもっと大事な日は(もともとカレンダーで赤い数字で書かれている)祝日ではなく、黒色ではあるけどご家族の誕生日や、パートナーとの記念日、ご家族が亡くなられた日など、身近な人との日だと思います。
祝日なんかより大切な日なので忘れることがないようにカレンダーに赤くしておきましょう。