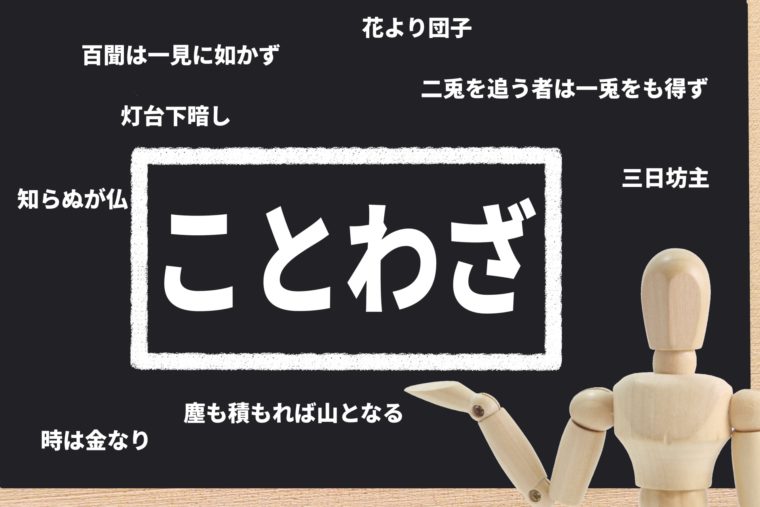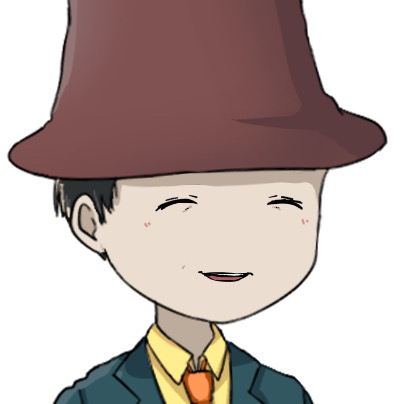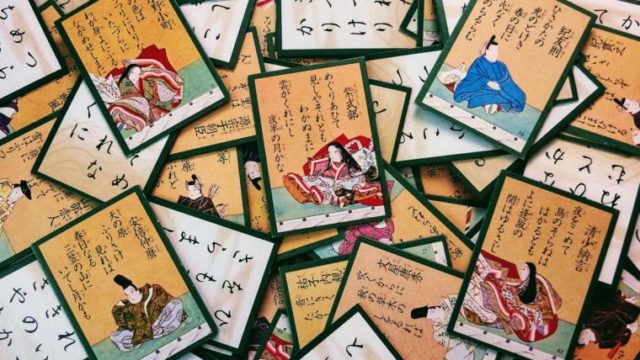みなさんは好きなことわざはありますか?今回はことわざをご紹介します。一言でことわざといっても今回は面白いことわざを集めました。
例えば「商いは牛のよだれ」ということわざ。「商い=商売」ということは分かると思いますが、どうして商売が「牛のよだれ」だと思いますか?
また、くすね取るといった意味で皆さんもご存じの「ネコババ」という言葉。実はあることわざを省略したものでした。
などなど、面白いのはもちろん、新たな発見もあるモノを集めました。ここで知ったことわざをどこかで使いたくなること間違いないでしょう。
目次
- 面白いことわざ
- 坊主の花かんざし
- やすりと薬の飲み違い
- 団子に目鼻
- 夜目(よめ)、遠目、笠の内
- イタチの最後っ屁
- 商いは牛のよだれ
- 磯の鮑(あわび)の片思い
- 牛の小便と親の意見
- 芋の煮えたも御存じない
- 頭の上のハエを追え
- 老いたる馬は道を忘れず
- 秋の扇
- 悪妻は百年の不作
- 東男(あずまおとこ)に京女(きょうおんな)
- 痘痕(あばた)も靨(えくぼ)
- 石に漱(すす)ぎ、流れに枕す
- あの声でトカゲ食らうホトトギス
- 一杯は人酒(ひとさけ)を飲む、二杯は酒酒(さけさけ)を飲む、三杯は酒人(さけひと)を飲む
- 瓜(ウリ)に爪(ツメ)、あり爪に爪なし
- 鬼も十八、番茶も出花
- 金(かね)の草鞋(わらじ)で尋ねる(または「探す」)
- 勘定合って銭足らず
- 鬼籍(きせき)に入る
- きつねを馬に乗せたよう
- 米の飯と天道様はどこへ行ってもついて回る
- 小姑(こじゅうと)一人は鬼千匹に向かう
- 魚は殿さまに焼かせよ、もちは乞食(こじき)に焼かせよ
- 亭主の好きな赤烏帽子(あかえぼし)
- 泥棒(または「盗人」)に追い銭
- 女房と畳は新しいほうがよい
- 盗人の昼寝
- 猫糞(ねこばば)を決め込む
- 屁を放って尻をすぼめる
- 煩悩の犬は追えども去らず
- 味噌も糞も一緒
- 娘一人に婿(むこ)八人
- 幽霊の正体見たり枯れ尾花
- 最後に
面白いことわざ

坊主の花かんざし
持っていても役に立たないものを表す言葉。坊主にはかんざしなんか必要ないですよね。同じ意味のことわざに「馬の耳に念仏」「猫に小判」「豚に真珠」などがあります。
やすりと薬の飲み違い
(言葉では)ちょっとした違い。しかし実際は大きな違いがあり、早合点は大変なことにつながるという意味。「や」と「く」を「8」と「9」とも掛けたことわざです。
団子に目鼻
団子のような丸くて良い顔をしているという意味。同じような表現に「卵に目鼻」もあります。これに対し「鍋蓋(なべぶた)に目鼻」ということわざは馬鹿にした表現です。
夜目(よめ)、遠目、笠の内
主に女性についての表現。夜や遠くから見る女性、また笠をさしている女性は顔がはっきり見えないので綺麗に見えるという言葉。
失礼な話ですよね。
イタチの最後っ屁
困った時の最終手段という意味。追い詰められたイタチは最後の手として臭いおならを放つことからできました。
イタチのおなら、臭いと聞きますが、嗅いだことある方はいらっしゃいますか?
商いは牛のよだれ
商売は牛のよだれのように細く、長く、切れ目がなく、また辛抱強く気長に続けることという意味。
牛のよだれ、臭そうですよね。
磯の鮑(あわび)の片思い
片思いのことをしゃれて言う言葉。(「ひな人形の飾り方」でも紹介しましたが)二枚貝のハマグリならば絵合わせのように相手がありますが、アワビの貝殻には相手がないことからできました。
アワビは巻貝の仲間なので相手はいつまでたっても見つかりません。
牛の小便と親の意見
牛の小便は1回が長く、また量も多いのですが肥料にはなりません。また、親の意見も同様。長いだけで子供に気持ちが伝わらないということ。
「牛」が入ったことわざ。小便であったり、よだれであったり。もう少しいい表現はないのでしょうかね。
芋の煮えたも御存じない
世の中のことに疎い(うとい)人のこと。からかうような表現です。お芋が煮えたかどうかの区別もつかない人という意味です。
頭の上のハエを追え
人をとやかく言ったり、世話を焼いたりするより先に、自分のことを行えという意味。
老いたる馬は道を忘れず
いろんな経験を積んだ人は方針(道)を誤らないということ。
秋の扇
男性の愛が薄らぎ、見捨てられた女性を例えた言葉。夏が去り必要がなくなった扇に例えられました。
悪妻は百年の不作
悪い奥さんは一生旦那を不幸にするということわざ。
東男(あずまおとこ)に京女(きょうおんな)
男性は江戸のたくましい人、女性は京都のしとやかで優しい人が良いという意味。
痘痕(あばた)も靨(えくぼ)
痘痕とは天然痘(てんねんとう)という病気が治った後に残る跡のことです。好きな人やひいき目で見ている人の痘痕(欠点)も靨(長所)に見えてくるということ。
石に漱(すす)ぎ、流れに枕す
負け惜しみが強かったり屁理屈を言って自論を正当化したりすることを例えた言葉。中国が晋の時代の政治家の言い間違いからできました。「石に枕し、流れに漱ぐ」と言いたかったのですが、「石に漱ぎ、流れに枕す」と言ってしまいました。この人、正直に間違いを認めればよかったのですが、「石に漱ぐとは歯を磨くことで、流れに枕すとは耳を洗うことだ」と屁理屈を言ったところからこの言葉ができました。
あの声でトカゲ食らうホトトギス
人や物事は見かけで判断できないということ。このことわざは江戸時代の俳人、宝井其角(たからいきかく)の俳句です。綺麗な声で鳴くホトトギスがトカゲを食べていたことから生まれました。
一杯は人酒(ひとさけ)を飲む、二杯は酒酒(さけさけ)を飲む、三杯は酒人(さけひと)を飲む
お酒の飲む量への注意を促す言葉。人が飲んでいたお酒に段々飲まれていってしまうことを表します。
瓜(ウリ)に爪(ツメ)、あり爪に爪なし
似た漢字「瓜」と「爪」の覚え方。瓜という漢字には(中の縦棒の下に)にツメがあるということです。
鬼も十八、番茶も出花
容姿が悪くても年頃になれば美しくなるという意味。鬼も18歳の年頃になると美しく、また番茶(それほどいいお茶ではなくても)もお湯を注いだばかりのものはいい味が出るということからできました。
金(かね)の草鞋(わらじ)で尋ねる(または「探す」)
辛抱強く歩き回って探す。得ることが難しい物事を例えて言います。
勘定合って銭足らず
考えた理論と実際が一致しないことの例えです。
鬼籍(きせき)に入る
死ぬことをいいます。「鬼籍」とはお寺で死んだ人の名前や死亡年月日を記す帳面のことです。これに記入されるということは「死んだ」ことを意味するからです。
きつねを馬に乗せたよう
動揺して落ち着きがないこと。また、言うことが曖昧でつかみどころがなく、信用できないこと。きつねは馬に落ち着いて乗っていられないという例えです。
米の飯と天道様はどこへ行ってもついて回る
どこへ行っても太陽(天道様)の光が照らすように、どんなに苦しい境遇にあっても「米の飯(最低限の食事)」を食べることはできるという意味。
小姑(こじゅうと)一人は鬼千匹に向かう
小姑とは義理の兄弟姉妹のこと。お嫁さんにとって小姑さんは鬼千匹と同じくらい面倒で厄介な存在だということ。
魚は殿さまに焼かせよ、もちは乞食(こじき)に焼かせよ
仕事を始め、何事にも向き不向きがある。だから適材適所が必要だということ。魚はあまりひっくり返さない方が上手く焼けるので、どっしり構えているお殿様に。また、お餅は焦げないように絶えずひっくり返さなければならないので、がつがつした乞食に焼かせた方がいいことからできました。
亭主の好きな赤烏帽子(あかえぼし)
どんなにおかしいと思っても一家の主(あるじ)の言うことには従わなければならないということ。烏帽子というと黒色が一般的ですが、亭主(主)が赤色の烏帽子が好きなら、家族も同調すべきだということから生まれました。
泥棒(または「盗人」)に追い銭
損した上に、さらに損害を受けることの例え。泥棒に物を取られた上にお金まで取られること。
女房と畳は新しいほうがよい
何でも新しい方が新鮮な気分がして気持ちが良いことをいいます。
男性目線のことわざですよね。今の女性は「亭主と畳は新しい方がいい」と言うのかもしれませんね。
盗人の昼寝
どんなことにも理由があるということ。盗人が昼寝するのは夜泥棒に入るという理由があるということから作られました。
猫糞(ねこばば)を決め込む
素知らぬ顔をして悪いことをする、悪いことをしても知らないふりをするという意味。また、他人の物を隠して自分のものにしてしまうという意味もあります。糞をした猫は知らない顔で砂をかけ、隠してしまうことからできました。
「ネコババ」はこのことわざが略された言葉です。昔は汚いもののことを「糞(ばば)」と呼んでいました。諸説ありますがババ抜きの「ババ」も「糞」といわれています。
屁を放って尻をすぼめる
自分がした失敗に対して慌ててごまかし、取り繕うこと。
おならをしてしまい「あっ」と思い慌ててお尻に力を入れる。こんなこともことわざになっているのです。
煩悩の犬は追えども去らず
犬を追い払おうとしてもどこまでもついて来るのと同じように、煩悩から離れようと思っても離れることができないという意味。
犬を追いかけるのではなく追っ払うという意味の「追う」です。
味噌も糞も一緒
性質が全く異なるものを区別することなく一つにまとめてしまうこと。
味噌汁ではなく○汁?
「うんこ味のカレー」と「カレー味のうんこ」どちらも同じってことですよね。
娘一人に婿(むこ)八人
選ばれるのは1つなのに対して応募数が多いことの例え。
倍率8倍の狭き門です。
「かぐや姫」を思い出しますよね。
幽霊の正体見たり枯れ尾花
何事も怖いと思っていると何でもないものまで恐ろしく感じてしまうこと。「尾花」はススキの穂のことで、「幽霊が出る」と噂の場所の枯れたススキの穂が幽霊に感じるということです。
最後に
いかがでしたか?中国・晋の政治家が言い間違えた「石にすすぎ、流れに枕す」なんて考えただけでおかしいですよね。例えば洗濯洗剤を石ですすぐ。また水の流れを枕にして眠るなんて笑えてきますよね。
またネコババの「ババ」は「糞」で猫の糞でした。「商いは牛のよだれ」、牛のよだれ以外にもっといいものは思いつかなかったのでしょうかね。
最後にもっとみなさんが知っていることわざで、おかしなものを1つお伝えします。みなさん「七転び八起き」はご存知かと思います。どんなに失敗しても立ち向かう精神を表す言葉ですよね。実はこれ、考えるとおかしいのです。7回転んで8回起き上がることはできませんよね?もし7回転び8回起き上がるのであれば、最初は転んだ状態から始まっていないと不可能です。
今回は日本のことわざの実を紹介しましたが、海外にはお国柄が出たことわざもたくさんあります。例えば、ドイツで言えばドイツにはソーセージが出てきたり、ブルガリアではヨーグルトが出てきたりします。
ことわざは昔の人の経験により生まれた技術や知識を表す言葉です。今回は一部のことわざしか紹介できませんでしたが、これを機にいろんなことわざを探してみてください。