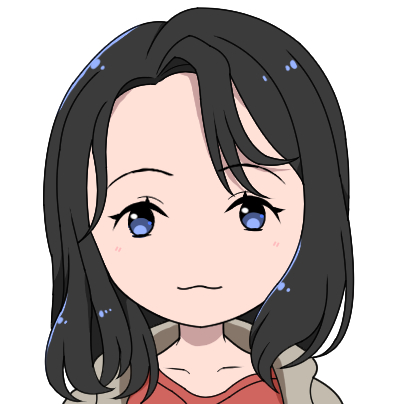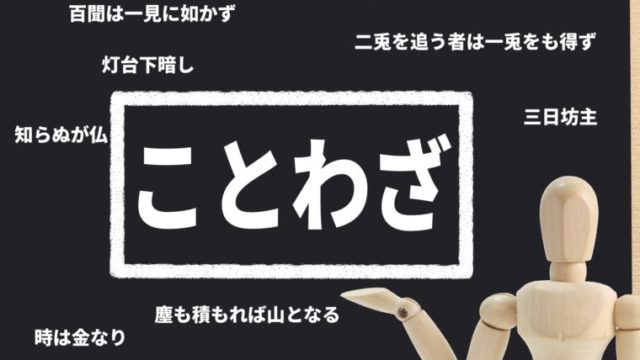あなたは「都々逸(どどいつ)」を知っていますか?江戸から明治にかけて流行した唄のひとつです。 俳句は「5・7・5」のリズムで読まれますが都々逸は「7・7・7・5」のリズムで構成されているのが特徴です。都々逸の中でも有名な「ザンギリ頭を叩いてみれば文明開化の音がする」などは聞いたことがあるのではないでしょうか?
三味線などと合わせて即興で唄われたり、時には韻を踏んでみたりと言葉遊びの要素も含まれるため、広く世間に親しまれた都々逸には、恋や愛を唄ったものも数多く存在します。この記事では恋愛を題材にした切ない都々逸を5つピックアップして紹介します。100年以上前に綴られた愛の唄を、ぜひ楽しんでみてください。
目次
三千世界の烏を殺し、主と朝寝がしてみたい -高杉晋作(諸説あり)
江戸花街の遊女が客に対して朝方の睦言(むつごと)の情景を唄ったものと解釈されています。高杉晋作の作と云われていますが、諸説あるようです。
「三千世界」を簡単に説明すると、「ありとあらゆる世界」という意味です。「烏を殺し」は鳴き声がうるさいから殺してしまうという意味ではなく、江戸時代の遊女は客を繋ぎとめるために「起請文(きしょうもん)」という誓約書を書いて渡していました。「仕事で他の客に身体を許しても、貴男だけが本命です。だから心だけは他の者には許さないことを誓います」という内容です。
この約束は熊野神社の護符の裏に書くのが決まりで、誓いを破れば熊野の神の使いである鳥が死に、その祟(たた)りが降りかかるとされていました。「今まで起請文を渡してきた男たちを皆裏切り、その結果全ての世界の鳥が死ぬことになっても、本当に大好きなあなたと一晩中一緒に過ごして朝遅くまで寝ていたい。それで祟りが降りかかっても構わない」という想いを綴った唄なのです。
覚悟を決めた愛の前では恐れなど何もないのかもしれませんね。
お前死んでも寺にはやらぬ 焼いて粉にして酒で飲む -詠み人知らず
本当にどうしようもなく愛してしまった相手を誰にもとられたくない、死が2人を分かつことも許せない。という想いを唄ったものです。
「何があっても離れたくない。でも命には限りがある。ならば寺には送らず骨を砕いて酒で飲んで、自分の一部として共にいよう」という、強い独占欲を感じます。またこの唄は同時に「死ぬときは一緒だ」という意味も込められています。愛した人を誰にもとられたくないという想いは、時に狂気的な方向へ駆り立ててしまうのかもしれません。
ちょっと怖い唄ですが、相手を深く想っている気持ちが伝わりますね。
逢うた夢みて笑うてさめる あたり見まわし涙ぐむ -詠み人知らず
愛しい人との夢を見て笑って目を覚ましたのに、起きたらその人がいない現実に涙する。という意味の唄です。
夢は残酷なほどに美しい幻を見せるもので、もうそこにいるはずのない愛しい人をありありと映し出します。その甘さに身をゆだねて笑っているのもつかの間、目が覚めれば誰もいない現実を突きつけられるのです。
まわりを見渡して必死に想い人を探して、夢だと自覚したその時の気持ちはまさに「突き落とされた」ような感情なのでしょう。ただひたすらに夢の中の甘いひと時を思いながら涙を流すのです。
唄い主の謙虚で美しい想いが儚く綴られています。
思い出せとは忘るるからよ 思い出さずに忘れまい -詠み人知らず
「思い出す」という行為は「忘れている」からこそできる行為なのだ、という意味を少し卑屈っぽく恋人に唄ったものです。
「思い出す」という行為は一見温かく感じますが、忘れていなければ思い出す必要などないのです。つまり「1度は忘れてしまった」という証明に他ならないということです。忘れられないことはいつまでも心の中に残るものです。
ですが「過去の恋愛を何度も思い出してしまう」と悩む人も、思い出している限り1度は忘れられている証拠。いつかは心を切り替えて前へと進むことができるというポジティブな解釈もできるでしょう。
この唄を綴った人は、卑屈っぽく言ってしまうくらい、相手に忘れてほしくなかったのかもしれませんね。
あの人の どこがいいかと尋ねる人に どこが悪いと問い返す -詠み人知らず
愛する人の味方が自分1人でも構わないという美しい切り返しを唄ったものです。
好きな人の魅力を他人に理解してもらうことは難しいもので、外から見えるものは容姿や雰囲気といったものだけです。たとえ愛する人の魅力が世の人達に理解されなくても、自分だけは理解しているし愛している。周りにどう言われてもこの気持ちは変わらない。という直情的で深い愛情を感じられる唄です。
好きな人に理解されていれば、それだけで十分なのかもしれませんね。
さいごに
今も昔も人が人を愛する心は変わりません。都々逸は現代ではあまり馴染み深くないものになりましたが、100年以上経った今でもこうして唄として語られ、そこから多くの人が共感を得ています。庶民から親しまれた都々逸だからこそ表現できる自由で時にいびつな愛の形は、飾りのない美しさを感じます。
現代での都々逸は落語や舞台などで耳にすることもあります。書籍も多く出ているため、興味があればぜひ都々逸の世界に触れてみてくださいね。