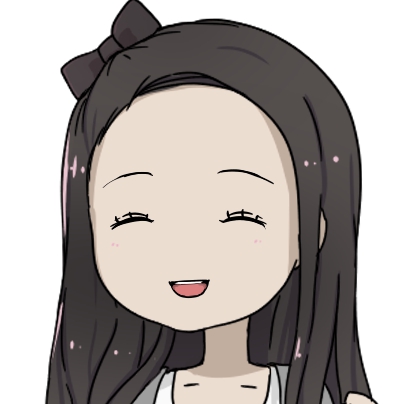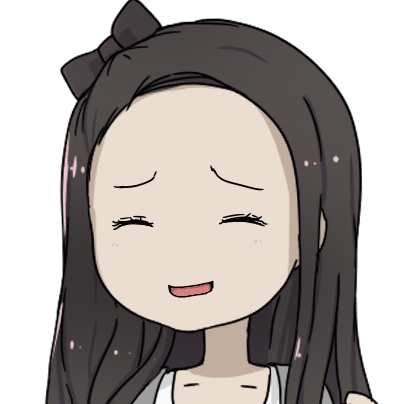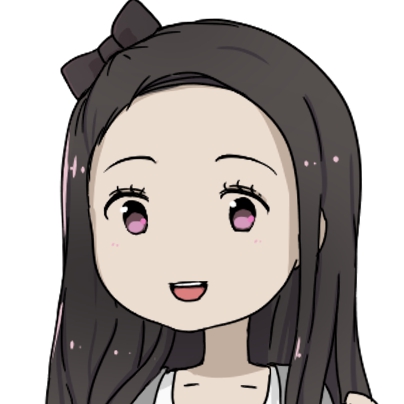みなさん、今年のお盆はどうやって過ごすか、もう決まっていますか?家族で旅行に出かけたり、実家に帰って家族と過ごしたり、充実したお盆休みを過ごしたいですよね。でも、お盆とは一体どうやって過ごすのがいいのでしょう?
本来はどうやって過ごすものなのか気になりますよね。地域によってお盆休みの過ごし方や風習は変わります。旅行などにお出かけするのもいいですが、今年はご先祖様に感謝する日にしてみませんか?
地域によってお供えするものが変わったり、ご先祖様のお迎えの仕方が変わったりします。今日は本来のお盆休みの過ごし方をご紹介していきます。そもそもお盆って何?という疑問にも答えます!ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
目次
お盆とは?

お盆のことを「盂蘭盆会(うらぼんえ)」というのが正式な名称です。ご先祖様があの世から、この世に戻ってくる期間です。ご先祖様が生前に過ごした自宅などにお迎えをします。そして、再びあの世に戻るのですが、あの世でも幸せに過ごせるようにと願い、あの世へと送ります。
初盆とは?
故人が亡くなって初めてのお盆のことを「初盆」といいます。初盆は一般的に盛大に行われることが多いです。初物の野菜や果物、故人が好きだった食べ物、花などをお供えします。
そして、身内を呼んでお経をあげてもらうのです。初盆は故人が家まで帰ってくるのに迷ってしまわないように、盆提灯の他に白一色の盆提灯を飾ることもあります。
お盆と呼ばれる期間は?

全国的には8月15日を中日にして、13日~16日の4日間をお盆休みとすることが多いです。東京や神奈川の一部の地域では1か月早い、7月13日~16日の4日間がお盆休みです。また他にも8月下旬から9月初旬をお盆とする地域もあります。沖縄では旧暦の7月13日から15日の3日間がお盆休みとしています。
お盆の時期が違う地域があります。
お盆の起源

盂蘭盆会(うらぼんえ)は仏教の盂蘭盆経(うらぼんきょう)が由来だと考えられています。盂蘭盆(うらぼん)はサンスクリット語のウラバンナ(逆さ吊り)が起源。これには言い伝えがあり、お釈迦様の弟子の一人である目連(もくれん)が関係しています。
その言い伝えとは?目連は亡くなった母が、地獄で逆さづりの刑を受けていることを知ります。母を助けたい目連は、お釈迦様に助ける方法を聞きます。お釈迦様は「旧暦である7月15日に供養しなさい」と伝えました。それからお盆の風習が始まったのです。
目連の母は地獄で刑を受けていました。何か悪いことをしてしまったのでしょうか?
お盆の期間中にすること

お盆の過ごし方はご先祖様を供養するためにあります。法要することやお墓参りに出向く、盆踊りで踊りを奉納するのも正しいお盆の過ごし方だといえます。
夏祭りに出かけたり、花火を見に行ったりするのも楽しいです!
お墓参りの作法

お墓は先祖の体であるといわれており、頭から水をかけることは良くありません。そのため、タワシなどでゴシゴシ洗うのも良くないとされています。やわらかい布やスポンジで優しく洗いましょう。お供え物の水は、水受けに入れてお供えします。
花をお供えする時は故人の好きな花を選ぶと良いでしょう。しかし、トゲのあるバラや、毒があるヒガンバナやスイセンは適していません。またツバキも花の落ちる様子が、首が落ちることを想像するためお供えするには良くありません。
お供えしたものはカラスなどに荒らされてしまうことがあるため、持ち帰るようにしましょう。
精霊馬の意味

先祖をお迎えするためのお供え物のキュウリとナス。これは「精霊馬(しょうりょううま)・精霊牛(しょうりょううし)」と呼ばれ、先祖をお迎えに行くキュウリ(馬)と、あの世に帰る時に乗るナス(牛)意味しています。また、馬は速く走れることから先祖を早く迎えに行き、帰りは牛に乗せてゆっくり帰ってもらいます。
キュウリとナスに割りばしをさして、馬と牛を作ります。初めて見た時は「何をしているのだろう?」と、おどろきました。
地方によって変わるお盆の過ごし方

ここからは少し変わったお盆の過ごし方をご紹介していきます。あなたの地域はどんな過ごし方をしていますか?
長崎県の五島列島など
なんとお墓で花火をします。花火をして故人を喜ばせるという意味と、花火の音で悪魔を払うという意味があるのです。この風習は江戸時代から続いています。
岩手県の花巻市や北上市など
墓石の上にお供えものとして昆布をかけます。長い昆布をハシゴにして、先祖があの世から帰ってくると考えられています。
瀬戸内海にある愛媛県や広島県の島など
遺影を背負って盆踊りをするという風習があります。去年の秋以降に亡くなった人の遺族が遺影を背負います。亡くなった人の霊が子孫と一体になる、一緒に喜び、感謝をし合うと考えられているのです。
沖縄県
旧暦である7月13日がウンケー(お迎え)、15日がウークイ(お送り)といい、本島ではエイサー、八重山諸島では歌や踊りを披露するアンガマという風習があります。
まとめ
お盆の過ごし方や風習はいかがでしたか?地域によっていろんな風習がありました。お墓で花火をするのは長崎県の風習でしたが、老若男女楽しめてステキなお墓参りですよね。
今までは特に予定もなくダラダラと過ごしていた方も、今年のお盆はご先祖様と一緒に過ごす日にしてみませんか?きっとご先祖さまも喜んでくれるでしょう!ステキなお盆休みを過ごしてくださいね。