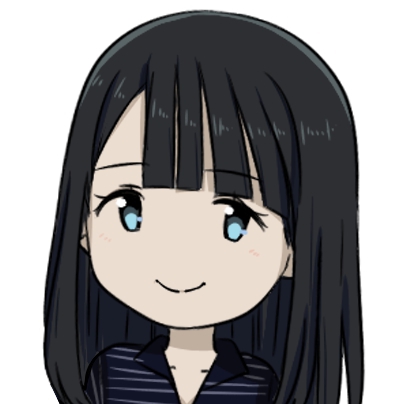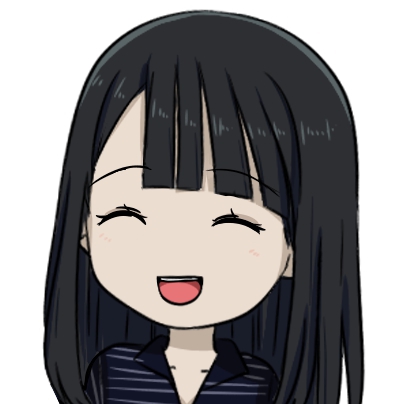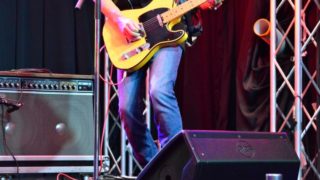みなさんは花の名前を漢字でいくつ書けますか?簡単な物でいうと、日本の春の花「サクラ」。「サクラ」は日本人なら成人していれば、大抵の方は書けるはずです。では、同じ春の植物で「つくし」や「チューリップ」はどうでしょう?すぐに思い浮かべることできますか?難しいですよね。答えは記事の中にあります。
この記事では、そんな漢字で書くと難しい花の名前を10選ご紹介します。この記事を読んで家族や友人・恋人とクイズを出し合うのも面白いですよね。ぜひ、最後までお読みください。最後には、みなさんの知っている身近なあの花の豆知識もご紹介しています。そちらの記事もぜひ、ご覧ください。
目次
月桂樹 (げっけいじゅ)


月桂樹は「げっけいじゅ」と呼びます。月桂樹と呼ぶと馴染みがないかもしれませんが、スーパーなどで当たり前に販売されている、あるスパイスのこといいます。
そのスパイスは、料理の香りづけで主に使用される「ローリエ」です。「ローリエ」の和名が月桂樹になります。「ローリエ」はフランス語です。英語では「ローレル」といいます。
大手酒造メーカー「月桂冠」のロゴには月桂樹の葉が描かれています。
仙人掌 (せんにんしょう)


仙人掌は「せんにんしょう」と読みます。これは「サボテン」のことをいい、日本で「サボテン」を漢字表記する場合はこの漢字が使われることが一般的です。仙人掌と表記する以外に「覇王樹」と表記されることもあります。
サボテンは育てやすいという理由から、近年日本で人気があります。
土筆 (つくし)


土筆は「つくし」のことです。読み方も同じです。しかし「つくし」は植物ではありません。「つくし」はスギナという植物の茎の部分のことをいいます。一説によると「土に刺さった筆」に見えたことから、この漢字が付けられたといわれています。
風信子 (ヒヤシンス)


風信子は「ヒヤシンス」のことをいいます。「ヒヤシンス」の漢字「風信子」は当て字です。これは「ヒヤシンス」が江戸時代後期に伝わった時に、付けられたといわれています。
蒲公英 (タンポポ)


蒲公英は「タンポポ」のことをいいます。中国ではタンポポを「蒲公英(ほうこうえい)」と表記します。「タンポポ」は日本で付けられた和名です。「向日葵(ひまわり)」や「紫陽花(あじさい)」も「タンポポ」と同じように、中国の漢字が使われ日本の和名が付けられた花です。
タイトルの「蒲公英」は「タンポポ」でした!
躑躅 (ツツジ)


躑躅は「ツツジ」のことをいいます。「躑躅」は「てきちょく」ともいい「てきちょく」は「足が止まる・躊躇(ちゅうちょ)」するなどの意味があります。「足が止まるほど綺麗な花」という意味でこの漢字が付けられました。
植物の漢字には「草冠(くさかんむり)」が使われることが一般的です。躑躅のように植物の漢字に「あしへん」が使われることは珍しいです。
緋衣草(サルビア)


緋衣草は「ひごろもそう」といいます。日本では「サルビア」のことを指します。サルビはラテン語で「癒し・健康」を意味する「salvus」が語源です。サルビアは他にも「来路花」と表記されることもあります。
わたしは、幼稚園のころサルビアの密を吸うのが好きでした!甘くて美味しかったです!
鬱金香 (チューリップ)


鬱金香は「チューリップ」のことをいいます。「チューリップ」が「ウコン(鬱金)」の香りに似ていたことから、この漢字が使われるようになりました。
チューリップの臭いを嗅いだことありますか?
燕子花 (カキツバタ)


燕子花は「カキツバタ」のことをいいます。「カキツバタ」の花が、燕(ツバメ)の飛ぶ様子に見えたことから、この漢字が付けられたといわれています。「カキツバタ」には「燕子花」以外にも「杜若」と表記されることもありますが、詳しい理由は現在も分かっていません。
柘榴(ザクロ)


柘榴は「ザクロ」のことをいいます。原産国のイランから中国に伝わった際に「瘤(こぶ)」の形に似ていたことから「安石瘤(ザクロ)」と言われるようになりました。これが省略され「柘榴」として日本に伝わりました。
まとめ
いかがでしたか?みなさんの気になる、花の漢字ありましたか?最後にタンポポの豆知識を1つご紹介します。
みなさん「タンポポ=黄色」というイメージがありませんか?実は西日本の一部地域では「白いタンポポ」が自生しています。これは「シロバナタンポポ」という品種です。近年では、地球温暖化の影響で東海や関東地方にも自生しているとされています。
ぜひ、探してみてください。この記事を読んで「面白かった!」「誰かに話したい!」と思っていただけたら嬉しいです。最後までお読みいただきありがとうございました。