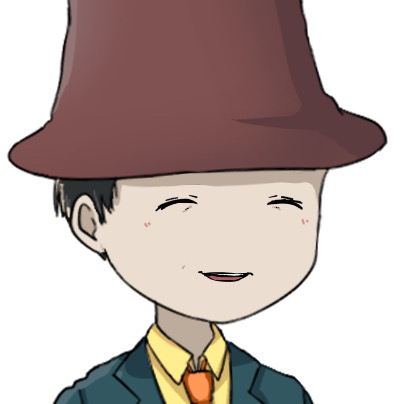みなさんのお宅では金魚や熱帯魚などの水槽はありますか?今回はそんな水槽にはびこるコケについてのお話です。
水槽やアクアリウムのガラス壁面、水草にまで発生するコケ。どれだけ掃除しても次から次へと発生する厄介な植物ですよね。なんと淡水に生きるものだけで15000種類もあると言われています。
今回はそんなコケについての雑学です。はじめに「コケとは何か」についてお伝えします。実は水槽に生えるコケは(「○○ゴケ」と付くものが多いのですが)コケではありません。
次いでコケが増える条件をお伝えします。なんと「水を入れ替えることでコケが発生しやすくなる」なんてこともあります。
そのあと大きく6種類に分け、コケの特徴、性質や対策などを紹介します。
「♪コケのー、むーすぅま~でー」お楽しみください。
目次
コケとは~水槽に生えるコケはコケではない!

熱帯魚などを飼う水槽に「コケが生えた」などとよく言います。しかし本当はこれ、コケではありません。コケは一般的に陸上で育つ植物で、(種子植物などにはある水分や栄養を運ぶための)維管束(いかんそく)がない植物のことを言います。
名前に○○ゴケなどと付いているものも多い(水槽に生える)コケ。実はコケ類ではなく、藻(も)の仲間「藻類(そうるい)」なのです。藻類には
- 真正細菌のバクテリア(藍藻)
- 単細胞生物の真核生物である珪藻、黄緑藻、渦鞭毛藻(うずべんもうそう)など
- 多細胞生物である海藻類(紅藻、褐藻、緑藻)
などがあります。淡水で生きる藻類は約15000種類もあります。
15000種類もある藻類。しかし、1つの水槽に発生するのは5、6種類ほどと言われています。
水槽に生えるコケ

ここからは水槽に生えるコケ(藻類)についてご紹介します。
水槽にコケ(藻)が生える条件
コケが生えやすい水槽にはいくつか条件があります。
(人口密度ならぬ)「魚口密度」の増加による水質悪化
熱帯魚が多く入った水槽ではコケが生えやすくなります。これは水質が悪くなりやすいからです。例えば
- 熱帯魚の糞:糞の汚れがコケの養分になります。
- エサの食べ残し:食べ残したエサも水質悪化をもたらし、コケの発生・成長を促します。
- 二酸化炭素の増加:個体数が増えると水中の二酸化炭素も増えます。コケも葉緑素を持っていて光合成をして成長していきます。だから二酸化炭素の増加はコケが増える要因になる。
などです。
水草の栄養分
水槽には水草も入れていますよね。水草を育てるための肥料もあげていると思います。この肥料が多すぎると水草のみならず、コケにも養分がいき、コケの成長まで促してしまうのです。
このように水中の栄養分が多いことは(赤潮が発生する時と同じ)「富栄養化」ということですよね。
魚の密度は
体長1cmほどの魚1匹に対して1Lくらいのエリア
があると魚にとってもストレスなく暮らせます。
水槽の場所・日光
先ほども書きましたが、コケも葉緑体を持った植物なので光合成をします。だから日光が当たる場所はコケの成長を促します。
水の入れ替え
先ほどは「水が汚れた富栄養化の状態ではコケが増えやすい」とお伝えしました。「ならば水を入れ替えればいいのか」というと、そういうわけでもありません。
実は水を入れ替えると水槽に入れている水草の調子が下がります。だからコケが生えやすくなるのです。特に新たな水槽を立ち上げる時などは増えやすいので注意が必要です。
水草もそれまでの慣れた環境が変わると、慣れるまで体調が悪くなるのです。
新たな水槽を立ち上げる時は石巻貝といった生命力の強い生き物を少し入れます。こうすることで自然に近い水に近付き、水草もすぐに慣れ、コケの繁殖対策に有効ではないかとも言われています。
水槽に生えるコケの種類
ここからは水槽に生えるコケの種類を6つに分け、それぞれについてご紹介します。
茶ゴケ(珪藻)
茶ゴケというだけあり茶色、または緑色のコケです。繁殖力が強いのが特徴で、ガラス面はもちろん、石や流木、水草にまで発生します。富栄養化状態の時や、新たに水槽を立ち上げた時などに発生しやすいコケです。
アオミドロ(緑藻)
糸のような長細いコケです。1つ1つは糸のようなのですが、増えると絨毯(じゅうたん)のように広がることもあります。水草にとろ~んと絡みつくこともあります。また伸びたアオミドロに熱帯魚の動きが妨げられる場合もある厄介者です。
これも栄養分の過剰状態のときに発生しやすいのですが、窒素や硝酸塩がなくても繁殖するコケです。
薄い緑色のコケ
水槽のガラス面にうっすら緑色につくコケ。これも栄養分の過剰により発生します。「このコケが付き始めた」ということは水槽内の水が汚れ始めた証拠です。逆に「このコケが付かなくなれば他のコケも大丈夫」という汚れ具合のチェックにもなります。
また、このコケは水槽に敷くソイル(土を粒状にして焼き固めたもの)が原因でも発生する事もあります。ソイルからは(微量ですが)アンモニアが発生します。このアンモニアがバクテリアにより硝酸塩へと変化して栄養分になるのです。
ソイルと言ってもいろんな種類があります。ソイルの中には糞尿を吸着して水の汚れを抑え、コケが発生しづらくするものもあります。
藍藻(らんそう)類
藍藻類はアメーバやヘドロのようなコケで、カビ臭いのが特徴です。水槽の底、ガラス面から水草の上にまでいたるところに繁殖します。この藍藻類はバクテリアです。部屋の明かりなどのわずかな光でも光合成をし、繁殖します。
藍藻類を取り除くには専用の薬を加える方法、また(昔、よく傷口の消毒に使われていた)オキシドールを添加する方法などがあります。
黒髭コケ
水草の縁(ふち)などに、まるでふわふわした毛玉のような黒色のコケが「黒髭コケ」です。このコケは水の流れが強い場所や光を多く受けやすいところで発生しやすいです。取り除くためには(人力で)ヘラを使う、水槽の水を取り替えるほか、水槽内の「リン酸を取り除く薬」を使う方法などがあります。
糸状のコケ
水草の葉につくことが多いこのコケは水草の成長に悪影響を与えます。葉っぱの上に細かな毛のように付くので英語ではhair algae(毛ゴケ)と言われます。このコケもやはり水中の栄養分増加で発生します。
先ほど紹介した「薄い緑色のコケ」が出始めたら、この糸状のコケも発生しやすい水質になっています。また、水草の光合成量が減ることで起こる水中の栄養分過剰でも発生します。
水草の光合成量の減少の原因としてはソイルが劣化、熱帯魚の増加、夏場などの気温上昇など、水槽内のわずかな環境変化で起こります。
最後に~ヤマトヌマエビでコケ解消
いかがでしたでしょうか?今回は厄介者、水中に発生するコケ(藻類)についてご紹介しました。
ほとんどのコケが富栄養化の状態により生える、生えなくするには水質をよくすることが分かったかと思います。またコケを除去するにはそれぞれ方法があり、薬を使う方法などコケにより違いがありました。
最後に薬や人の力を使わないコケの除去の方法をお伝えしたいと思います。それはヤマトヌマエビを一緒に飼うのです。このエビ、体長3~5cm、半透明なエビでコケを食べてくれるのです。
しかしこのヤマトヌマエビ、雑食なので小さい魚と大きめのエビを一緒にすると魚を食べてしまうことがあります。逆にエビの方も大きめの魚に食べられてしまうこともあります。エビと魚の大きさを考えながら飼ってください。
エビも加えて綺麗な水槽を楽しみましょう。