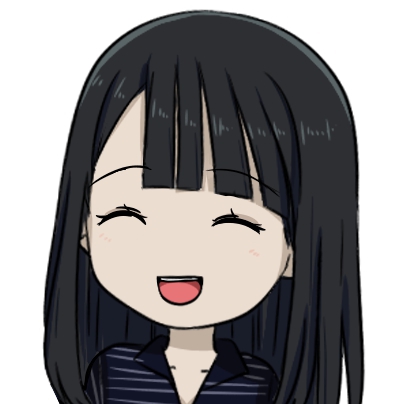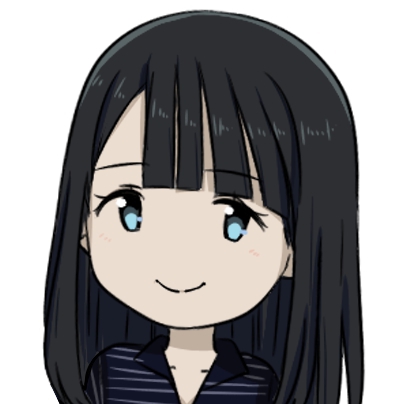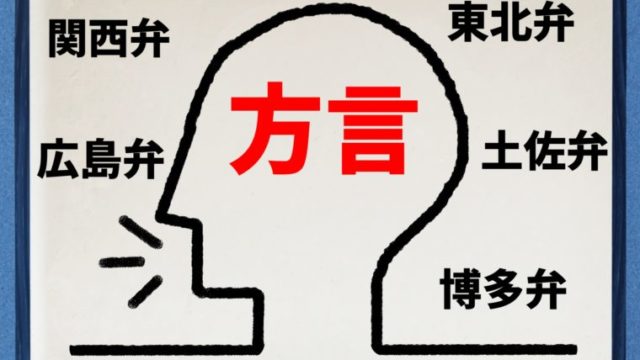皆さん「秋」といったら何を思い浮かべますか?「食欲の秋」「読書の秋」「運動の秋」など色々な「秋」がありますよね。私は食べることが大好きなので「食欲の秋」を思い浮かべます。美味しい食べ物もたくさんありますよね。「さんま」「栗」「サツマイモ」など。紅葉や植物も見頃な季節です。
秋には様々な豆知識や雑学が存在することをご存知でしたか?例えば「紅葉」でも「紅葉」と「黄葉」があります。普段食べている「竜田揚げ」も実は秋と深い関わりがあるのです。この記事では、明日、誰かに話したくなるような秋に関する雑学をご紹介していきます。よろしければ最後までご覧ください。
目次
秋の植物

秋の植物ついての雑学をご紹介します。
「紅葉」と「黄葉」の違い
「紅葉」と「黄葉」があります。「紅葉」はよく耳にする言葉ではないでしょうか?「黄葉」という言葉も存在するのです。「紅葉」も「黄葉」も名前の通りです。「紅葉」は「紅く色づく葉っぱ」のことです。「黄葉」は「黄色く色づく葉っぱ」を意味します。
イチョウは「生きた化石」と呼ばれている
私たちの身近にあるイチョウの木。実は恐竜が存在していた前の約2億年以上前からこの世に存在していたと言われています。約2億年前にはたくさんの種類のイチョウの木が存在していたと言われていますが、現在この世に生育しているは1種類のみです。
「もみじ」と「かえで」は葉っぱの形が違う
「もみじ」と「かえで」はどちらも「カエデ科カエデ属」に属しており、どちらも植物の分類としては「カエデ」になります。違うのは葉っぱの形のみです。見分け方は「5つ以上の深い切れ目が葉にあるもの」が「もみじ」。「切れ目が浅いもの」が「かえで」です。
コスモスの日がある
秋の花と言えばコスモスを思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?コスモスには「コスモスの日」があります。「コスモスの日」は毎年「9月14日」です。「9月14日」はホワイトデーから半年ということで、夫婦やカップルが愛を確かめ合う日です。お互いのプレゼントを交換する際にコスモスを添えて贈りあうという風習があります。
コスモスの日。ロマンティックで良いでよね!
秋の食べ物

秋には美味しい食べ物がたくさんあります。秋の食べ物の雑学についてご紹介します。
竜田揚げには秋と深い関わりがある
「竜田揚げ」。秋とは関わりがなさそうですが実は深い関わりがあります。「竜田揚げ」の「竜田」は奈良県の「竜田川」が由来です。「竜田川」は紅葉の名所となっており、竜田揚げを揚げた際に色が赤茶色く変わっていきます。それが竜田川に落ちる紅葉に見立てられていたため「竜田揚げ」と呼ばれるようになりました。
「モンブラン」と「栗」は関わりがない
「モンブラン=栗」と思われる方もいると思いますが全く関係がありません。「モンブラン」の名前の由来は、フランスとイタリアの国境にある「モンブラン山」から名付けられたました。「モンブラン」の形がその山に似ていることが由来です。
「マロン」は英語ではなく「フランス語」
「栗は英語でマロン」と思われている方もいると思います。実際にケーキ屋さんで栗を使ったケーキは「マロン○○」というような名前が多いからです。ですが「マロン」は英語ではなくフランス語です。英語で栗は「Chestnut(チェスナット)」と言います。
「松茸」や「椎茸」は日本でしか食べられていない
秋の食材と言えば「松茸」や「椎茸」ですが、「松茸」や「椎茸」は欧米人などからは好まれていません。その理由は「香り」です。欧米人などからは松茸や椎茸の香りは「履き続けた靴の匂い」や「お風呂に入り続けていない不潔な匂い」と思われています。そのため松茸や椎茸を多く消費するのは日本人です。
日本で一般的に食べられているカボチャは「パンプキン」ではない
日本で一般的に食べられているカボチャは緑のカボチャで「スクワッシュ」と言います。ハロウィンなどで多く使われるオレンジのカボチャが「パンプキン」です。
カボチャの名前の由来は「カンボジア」から
「カボチャ」の名前の由来はご存知ですか?カボチャの名前の由来は諸説ありますが、一番有力と言われているのが、約1500年以上前にポルトガルの船が日本にやってきました。そこに積まれていたのがカボチャです。そのカボチャはカンボジアから運んできたので「カンボジア」が訛って「カボチャ」になったと言われています。
銀杏を食べ過ぎると中毒症状が出る
銀杏を一度に大人が40個以上、子どもが5個以上食べると中毒症状が出ることがあります。主な症状は鼻血が出たり、痙攣を引き起こします。銀杏は栄養も豊富ですし秋にはとても美味しい食べ物ですが、食べ過ぎには注意しましょう。
松茸や椎茸はとても美味しいので、海外の方にも美味しさを知ってもらいたいです。
その他の豆知識

植物や食べ物以外にも面白い秋の豆知識があるので一部ですがご紹介します。
月の模様は国によって違う
日本では月の模様は「うさぎが餅つきをしている模様」と言われていますが、見え方は国によって違います。南ヨーロッパでは「カニ」、インドは「ワニ」、モンゴルは「犬」などがあります。この見え方の違いは国の文化や神話からだと考えられています。
鈴虫の鳴き声は電話を通すと相手には聞こえなくなる
鈴虫といえば秋の虫で、日本の童謡にも出てくる有名な虫です。そんな鈴虫の鳴き声の音の高さは約4,500ヘルツと言われています。普段私たちが使っている電話は300~3,400ヘルツの音を人の声の高さに合わせて伝えられているので、それより高い鈴虫の鳴き声は電話では聞こえません。
月の模様が国によって見方が違っているので、実際に海外に行って見てみたいです。
まとめ
いかがだったでしょうか?秋に関する雑学や豆知識をご紹介しました。「モンブラン」と「栗」が関わりがないのは農林水産省も公認で実際に農林水産省の公式のHPにも掲載されています。その他にも「コスモスの日」があったり、「竜田揚げ」が秋と深い関わりがあったりと面白い雑学がたくさんあります。
ぜひこの記事を読んで誰かに話してみたいと思ってくだされば嬉しいです。